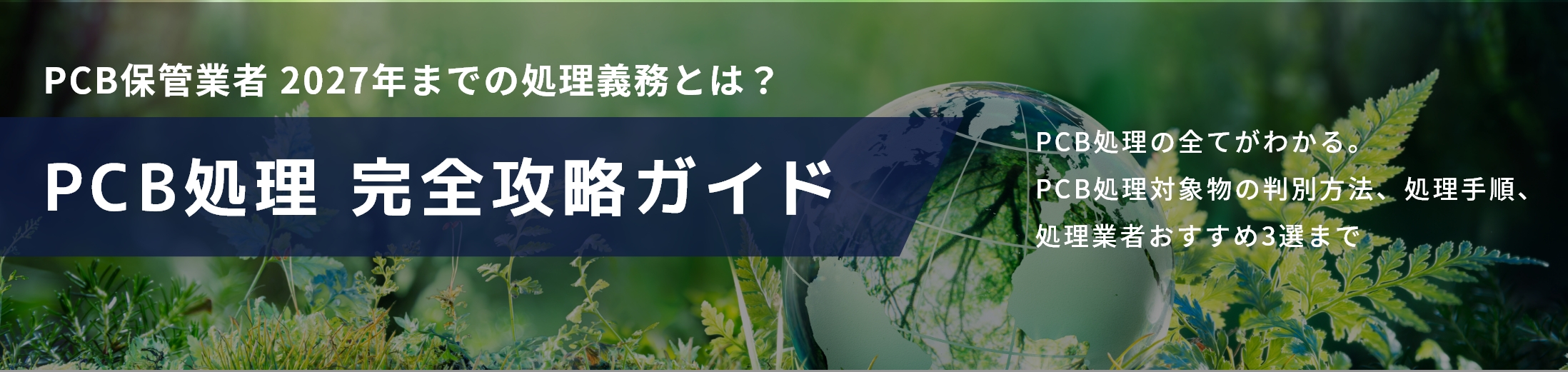PCB汚染物は、その有害性から製造や輸入が禁止されており、その該当性判断基準は対象物によって異なります。また、正確なPCBの検出と測定は、適切な分析方法を用いることが不可欠です。以下では、これらの基準と方法について詳しく掘り下げていきます。
目次
人体への毒性から製造や輸入が禁止になったPCB汚染物
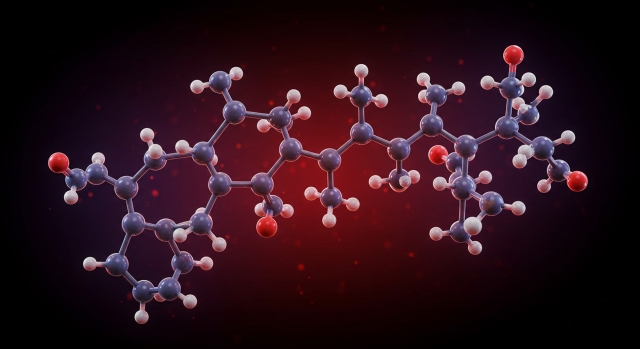
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、かつて絶縁体や潤滑油などに広く使用されていた化学物質です。しかし、その強い毒性から現在では製造・輸入が禁止され、PCBに汚染された物質も厳重な管理が求められています。ここでは、PCB汚染物の人体への影響やその特徴について解説します。
◇ポリ塩化ビフェニル汚染物は人体に有害

PCBは脂肪に溶けやすい性質を持ち、人体に取り込まれると脂肪組織に蓄積されやすく、長期間にわたって体内に残留するのが大きな特徴です。この蓄積により、さまざまな健康障害が引き起こされることが知られています。
主な症状には、皮膚疾患(発疹・湿疹、炎症、色素沈着)、目や鼻の刺激感、手足のしびれや麻痺、関節の腫れ、爪の変形、肝機能障害、免疫機能の低下、生殖機能への悪影響などが挙げられます。
また、妊娠中に母体がPCBにさらされると、胎盤を通じて胎児に影響が及び、出生体重の低下や神経発達の遅れといったリスクが高まるとされています。さらに、国際がん研究機関(IARC)は、PCBを「ヒトに対しておそらく発がん性がある(グループ2A)」に分類しており、発がん性の観点からも注意が必要です。
◇PCB汚染物とは

PCB汚染物とは、ポリ塩化ビフェニルを含んでいる、あるいは過去にPCBが使われていたことにより残留している物質や機器のことです。具体的には、トランス(変圧器)、コンデンサー、絶縁油、熱媒体、圧力調整装置などが該当します。ほかにも、蛍光灯やノンカーボン紙にPCBが混入しているケースもあります。
なお、PCBは自然界には存在しない、人工的に合成された化学物質です。PCBは、耐熱性や電気絶縁性に優れた性質から、工業用途において「夢の物質」とも呼ばれましたが、その一方で環境や人体への深刻な影響が次第に明らかになり、1972年に使用が禁止されるに至りました。
PCBには次のような特徴があります。
- 水にほとんど溶けない
- 沸点が非常に高い
- 熱による分解に強い
- 燃えにくい性質を持つ(不燃性)
- 電気を通さない性能が高い
これらの性質により、当初は極めて優れた工業材料とされていましたが、同時にこれらの「壊れにくさ」が環境中での長期残留性や生物体内への蓄積という形で深刻な問題を引き起こしました。
◇ポリ塩化ビフェニル汚染物には3種類ある

PCB汚染物は種類に応じて適切な処理補法を考える必要があり、焼却や洗浄などの複数の方式によって処理が実行されていることも特徴です。以下に3種類のPCB汚染物について記載します。
・感圧複写紙
ペンなどで文字を書き込んだ際の圧力を使って複写するための用紙であり、「ノーカーボン紙」と呼ばれています。現在はPCBの使用が禁止されていますが、昭和46年以前にはPCBを使用した感圧複写紙が生産されていました。環境省の発表では、現在も各地にPCBを使用した感圧複写紙が残っていると注意喚起されています。
・ウエス(繊維くず)
ウエスはPCBの染み込んだ繊維(繊維くず)のため、PCB処理の対象になっています。検疫中のPCB濃度が0.003mg/Lよりも多い場合、汚染物として扱われます。
・汚泥
PCBの染み込んだ汚泥もPCB汚染物となります。基準はウエスと同じく、検疫中のPCB濃度が0.003mg/Lよりも多い場合、汚染物として扱われます。
【あわせて読みたい】
▼ポリ塩化ビフェニル類とは?PCB規制や産業廃棄物業者選定を解説
PCB汚染物の回収が始まった経緯
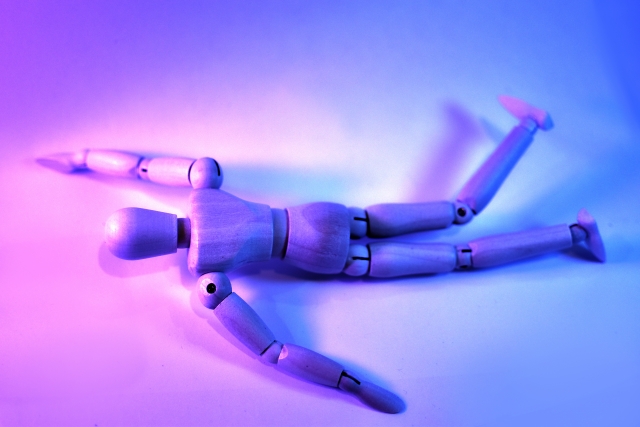
引用元:photo AC
PCBは持続的な環境汚染源となるため、その制御と回収が不可欠とされ、国際的な取り組みが進められてきました。以下では、PCB汚染物の回収が始まる過程やその背後にある主要な動機について詳しく解説します。
◇カネミ油症事件がきっかけ
PCBは、製造業界で使用されていましたが、昭和43年に発生したカネミ油症事件の発生により、状況が一変しました。カネミ油症事件とは、カネミ倉庫株式会社が製造したライスオイル(米ぬか油)製造過程の脱臭工程において、熱媒体として使用されていたPCBがライスオイル中に混入し、大規模な食中毒が発生した事件です。実際の症状としては、全身の倦怠感や色素沈着、食欲不振など様々なものがありました。カネミ油症事件以降、毒性が問題視され、昭和47年以降は製造がおこなわれなくなりました。
◇POPs 条約の発効

POPs条約(ストックホルム条約)は、残留性有機汚染物質(POPs)を国際的に規制することを目的とした条約で、2001年5月に国連環境計画(UNEP)の主導により採択されました。条約は、POPsに該当する化学物質の製造・使用・輸出入の制限や禁止、さらには廃棄物の適正な処理を求めています。
POPsとは、自然環境中で分解されにくく、長距離を移動し、食物連鎖を通じて生物の体内に蓄積されやすいという特性を持つ有害な化学物質のことを指します。代表的な例として、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、ダイオキシン、有機塩素系農薬(DDTなど)が挙げられます。
日本はこの国際的な動きを受け、平成14年(2002年)にPOPs条約を締結しました。これに伴い、化学物質審査規制法や廃棄物処理法の見直しが行われ、POPsの製造や輸入の原則禁止、ならびに保管・処分の厳格な管理が義務づけられています。
◇JESCOの処理体制の整備で加速した
すでに製造されたPCBの処理に向けて、民間主導によるPCB産業廃棄物処理施設設置の動きはありました。しかし、住民の理解を得られなかったことなどによりほぼ30年の長期にわたり処理がほとんど行われず、保管が続きました。
保管には、紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから、平成13年6月22日にPCB特別措置法が公布され、同年7月15日から施行されました。法律の施行により、国が中心となって日本環境安全事業株式会社(現:中間貯蔵・環境安全事業株式会社、略称JESCO)を活用して、拠点的な処理施設を整備することになりました。現在では全国5か所に処理施設が整備されています。
◇PCB特別措置法の改正

PCB特別措置法では、当初、PCB廃棄物の保管および処分の状況を都道府県知事に届け出ることや、施行日(2001年7月15日)から15年以内に処分を完了することなどが義務付けられていました。
しかし、処理の難しさなどから進捗が遅れたため、これまでに同法は処分期限の延長を含め、複数回の改正が行われています。2016年の改正では、PCB廃棄物の区分や処分ルールがより明確化され、確実な処理を促進するための規定が整備されました。主な改正のポイントは以下のとおりです。
- PCB廃棄物は、高濃度・低濃度・使用製品の3つに区分された。
- 高濃度PCB廃棄物は、処理期限の1年前までに処分することが義務に。
- 電気工作物にあたる製品は、電気事業法で対応されることに。
- 電気事業法に該当しない高濃度PCB使用製品も、PCB特措法の対象に追加。
- 原則として高濃度PCB廃棄物の保管場所変更は禁止(JESCOエリア内の移動のみ例外)。
【あわせて読みたい】
▼「夢の油」と呼ばれたポリ塩化ビフェニルの優れた性質と危険性
PCBの該当性判断基準と分析方法

PCBは含有量によって処理方法が変わる為、適切な分析方法で正しく測定する事が非常に重要です。以下で、判断基準と分析の注意点について解説します。
◇判断基準
PCB等の該当性判断基準としては対象物によって分けられています。以下に対象物とPCB汚染物等ではないことの判断基準を記載します。
| 対象 | 判断基準 |
| 廃油 | PCB含有量が0.5mg/kg以下 |
| 廃酸、廃アルカリ | PCB含有量が0.03mg/L以下 |
| 廃プラ | PCB含有量が0.5mg/kg超のPCBが含まれた油が付着していないこと |
| 金属くず | PCB含有量が0.5mg/kg超のPCBが含まれた油が付着していないこと |
| 陶磁器くず | PCB含有量が0.5mg/kg超のPCBが含まれた油が付着していないこと |
| 紙くず | 検液中の濃度が0.003mg/L以下 |
| 木くず、繊維くず | 検液中の濃度が0.003mg/L以下 |
| コンクリートくず | 検液中の濃度が0.003mg/L以下 |
| 汚泥 | 検液中の濃度が0.003mg/L以下 |
| その他 | 検液中の濃度が0.003mg/L以下 |
◇分析の注意点

PCB含有廃棄物の分析を行う際には、正確で信頼性のある測定結果を得るために、いくつかの技術的な注意点があります。特に定量濃度の設定や前処理の方法によって、結果に大きな差が生じる可能性があるため、各工程での慎重な対応が求められます。
定量濃度範囲の設定
PCB含有廃棄物は、5,000 mg/kgまたは100,000 mg/kg 以下かを判定します。
定量濃度範囲は、測定方法により異なり、主に 50 mg/kg から 5,000 mg/kg または 1,000 mg/kg から 100,000 mg/kg に設定されます。
濃縮又は希釈
測定に使用する簡易定量法によって、測定濃度範囲が異なるため、必要に応じて濃縮又は希釈を行います。抽出液が高濃度の場合、希釈操作により影響を受けずに測定できることがあります。
精製操作
抽出液の中に夾雑物が含まれ、測定に影響を及ぼす場合は、精製操作を行います。精製操作を省略できる場合もありますが、注意が必要です。
内標準物質の使い方
測定方法により、内標準物質の使い方が異なります。内標準物質は正確な測定に重要です。
抽出操作と評価
PCBの抽出操作は各機関の標準作業手順書に準拠して行い、詳細な操作記録を保持します。抽出効率と精度は、さまざまな方法で評価されます。投入回収試験、クリーンアップスパイクの回収率、二重測定などが一般的な評価指標です。
◇PCB廃棄物の主な分析方法
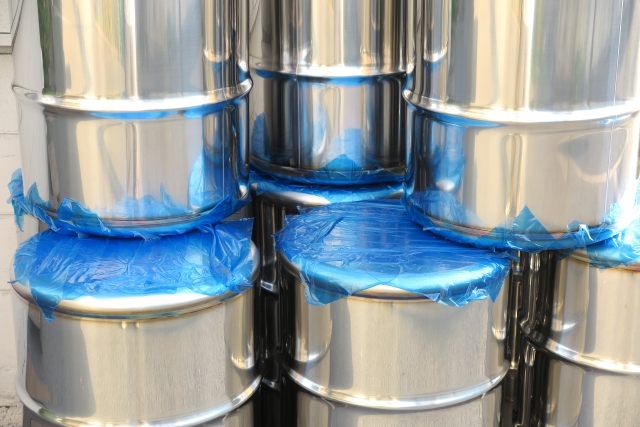
分析方法は対象物によって異なります。分析方法は以下の3種類があります。
洗浄液試験法
PCBが付着している可能性のある部材を溶剤で洗浄し、その洗浄液に含まれるPCB濃度を測定する方法です。機器を破壊せずに分析が行えるため、初期調査やスクリーニングに適しています。
ただし、PCBが部材表面から洗浄液中に十分に溶け出さない場合、実際の汚染よりも低い濃度で検出される可能性があり、過小評価のリスクがあります。そのため、洗浄溶剤の種類や洗浄時間、温度などの条件を適切に設定し、洗浄状態に偏りが生じないよう十分に管理することが重要です。
洗浄後の部材の汚染程度を調べるために、洗浄液濃度を測定する試験方法です。
抜き取り試験法
処理後の部材表面に残留しているPCBを検出するために、専用の溶媒やワイパーなどを用いて一定面積(一般に500cm²)を拭き取り、PCB濃度を測定する方法です。この方法は、表面汚染の有無を直接的に確認できる点が特徴です。
ただし、正確な結果を得るためには、対象となる部材の処理工程や状態を考慮することが重要です。異なる処理を受けた複数の部材をまとめて拭き取ると、汚染状態にばらつきが生じ、評価結果が不正確になる恐れがあります。
処理後の部材の表面の抜き取りを行ってPCB濃度を測定する試験方法です。
部材採取試験法

処理後の部材から試験を行う分を採取してPCB濃度を測定する試験方法です。
以下に対象物と分析方法を記載します。
・廃油・・・洗浄試験法
トリクロロエチレンやテトラクロロエチレン、または同等以上の洗浄力のある洗浄液を用い、循環洗浄や新たに洗浄した場合のみ、廃油(洗浄液)を「洗浄液試験法」にて検定します。
・廃酸、廃アルカリ、陶磁器くず、紙くず、木くず、繊維くず、コンクリートくず、汚泥・・・「特別管理産業廃棄物に係わる基準の検定方法」に沿う
環境省が示した廃酸や廃アルカリは環境省が示した「特別管理産業廃棄物に係わる基準の検定方法」に沿って試験を行います。
・廃プラ、金属くず・・・洗浄液試験法/拭き取り試験法/部材採取試験法
「洗浄液試験法」「拭き取り試験法」「部材採取試験法」から適した試験法を選んで検定します。試験方法によって判定基準値が異なることに注意が必要です。
【あわせて読みたい】
▼環境省のポリ塩化ビフェニル早期処理情報サイトで産業廃物対策
低濃度 PCB 汚染物の分析と注意点

低濃度PCB汚染物の分析には、わずかな量のPCBを正確に見つけ出す高い精度が求められます。そのため、分析方法や手順には特別な配慮と工夫が必要です。ここでは、分析の際に押さえておくべきポイントと、注意すべき点について解説します。
◇低濃度 PCB 汚染物分析のポイント

低濃度PCB汚染物かどうかを判断する基準は、PCB濃度が0.5 mg/kgを超えるかどうかです。このため、分析では0.5~50 mg/kgの範囲を正確に測定できることが求められます。特に、検出可能な最低濃度(検出下限値)は0.15 mg/kg以下である必要があります。
このような低濃度の分析では、通常のPCB含有廃棄物の分析と比較して、約100倍の検出精度が求められます。そのため、使用する機器や分析手順についても、より厳密な管理が必要です。
測定法によって対応可能な濃度範囲が異なるため、必要に応じて濃縮や希釈などの前処理を行い、測定に適した濃度に調整することが重要です。また、抽出液には他の物質(不純物)が混入していることがあるため、精製操作を省略せず、不要な成分を確実に除去する必要があります。
最後に、PCBを正確に抽出するための操作は、各機関が定めた標準操作手順(SOP)に従うことで、ばらつきの少ない安定した分析結果が得られます。
◇低濃度 PCB 汚染物分析の注意点

0.5 mg/kg(低濃度 PCB 汚染物の該当性判断基準値)というごくわずかな濃度のPCBを正しく測定するには、高性能な機器だけでなく、分析を行う人の技術も非常に重要です。測定ミスを防ぐためにも、きちんと整備された設備と、訓練された技術者が欠かせません。
この分析には、絶縁油中のPCBを測るときと同じように、きめ細かい精度管理が必要です。そのため、簡易測定法マニュアルのなかにある「精度管理」に関する指針が、そのまま低濃度PCB汚染物の分析にも適用されます。
マニュアルをよく読み、定められた管理方法に従って測定を行うことが、信頼できる分析結果を得るための大きな鍵となります。
【あわせて読みたい】
▼ポリ塩化ビフェニル汚染物の危険性は?PCB産業廃棄物の処理方法
低濃度PCB廃棄物の適切な保管

低濃度PCB廃棄物は、環境や人への影響を防ぐために、厳格な保管管理が求められます。適切な保管方法を理解し、確実に実践することが、安全な廃棄物処理への第一歩です。ここでは、保管の基準と注意すべきポイントについて解説します。
◇保管基準
・周囲に囲いを設ける
PCB廃棄物を保管する場所は、外部からのアクセスを防ぐために、しっかりと囲いを設ける必要があります。これにより、飛散や流出を防止し、関係者以外が誤って立ち入ることを防ぎます。
・掲示板の設置
保管場所には、「特別管理産業廃棄物を保管中」であることを明記した掲示板を、誰にでも見える場所に設置します。これにより、関係者以外が内容を誤認することなく、安全意識を高めることができます。
・飛散・流出・地下浸透防止
保管中の廃棄物が空気中に飛び散ったり、雨水などと一緒に流れ出したり、地中にしみ込んだりしないように、適切な設備を使用して確実に収納します。具体的には、鋼製容器やオイルパンなどが適用されます。
・密封・揮発防止
PCBが気化して大気中に漏れないよう、廃棄物は密閉できる容器に保管する必要があります。その容器は、熱や腐食に強い材質を選ぶことで、長期間の安全な保管が可能になります。
・屋内保管の推奨
可能であれば、専用の屋内施設に保管するのが理想的です。屋内であれば、雨風や直射日光から廃棄物を守ることができ、より安定した状態での管理が可能です。
・特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
保管場所には、専門の資格を持った「特別管理産業廃棄物管理責任者」を配置し、適切な管理体制を整えることが義務づけられています。特別管理産業廃棄物管理責任者になるためには、特定の資格または一定の学歴が必要です。
◇注意点

・定期点検
保管容器や周囲の施設は、定期的に点検を行い、腐食や破損、漏れがないか確認します。異常が見つかれば、すぐに補修や交換を行い、事故を防止します。
・ラベル貼付
PCB廃棄物であることがひと目でわかるように、容器に専用のラベルを貼り付けます。これにより、別の廃棄物と混同されるリスクを避け、誤って処分されることを防げます。
・地震対策
地震などによって容器が転倒したり、内容物が漏れ出したりするのを防ぐためには、容器の中に緩衝材を詰めるか、しっかりと固定しておく対策が必要です。これにより、万が一の災害時でも安全性が確保できます。
【あわせて読みたい】
▼PCB産業廃棄物の生物濃縮による影響とは?ポリ塩化ビフェニルの特性
PCB汚染物の収集・運搬

PCB汚染物の収集や運搬には、漏洩や拡散を防ぐための厳格なルールが設けられています。これらの基準を正しく理解し、確実に守ることが、環境と人の安全を守る第一歩です。ここでは、必要な防止措置と運搬時の注意点について解説します。
◇必要な防止措置
PCB汚染物の収集運搬事業者は、以下の条件を満たすことが求められます。
- PCB汚染物は、密閉性があり漏洩を防ぐ構造の容器に収納する。
- 運搬車両には、応急処置用の資機材や緊急時の連絡設備を備えておく。
- 運転者などの従事者は、PCBの性質や事故時の対応に関する知識と技能を有する。
- 対象地域の知事の許可に加え、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得している。
さらに、運搬時には主に次のような基準に従うことが求められます。
- PCBが人体や生活環境に害を与えないよう安全に取り扱う。
- 容器の密閉や防水処理により、飛散、雨水の浸入、地下への浸透を防止する。
- 容器を転倒させたり落下させたりするような乱暴な扱いを避け、丁寧に取り扱う。
- 他の物品を汚染しないよう、PCB汚染物は他の廃棄物と区分して収集・運搬する。
- 船舶に積載時、甲板上では食品類と6メートル以上離し、甲板下では同一区画に積まない。
◇運搬時の注意点
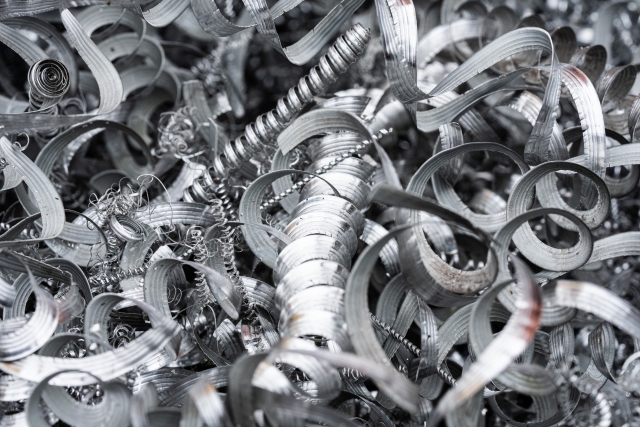
PCB汚染物は、長期間保管されている間に容器が劣化している場合があります。容器に腐食や亀裂、変形があると、運搬中にPCBが漏れ出す恐れがあるため、事前に丁寧な点検が必要です。
漏えい点検では、トランスやコンデンサー、またはそれらを収納している容器に破損や異常がないかを確認します。漏えいの兆候があれば、内容物を安全な容器に移し替える、あるいは必要な補修や保護措置を講じなければなりません。
このような点検は、事前の調査に加えて、積み込みや積み降ろしの際、さらには運搬中に車両が長時間停止する場面などでも実施が求められます。構造上の制約で点検が難しい場合を除き、目視によって漏えいや固定状況を確認することが基本です。
【あわせて読みたい】
▼PCB産業廃棄物の種類と代表的なポリ塩化ビフェニル使用製品
PCB汚染物の処分や運搬にも対応する業者3選
PCBの処分を安全かつ確実に実施するには、専門知識と許認可を持つ業者への委託が不可欠です。ここでは、PCB汚染物の処分や運搬に対応する代表的な業者3社をご紹介します。
◇丸両自動車運送株式会社

静岡県を拠点に全国対応でPCB廃棄物の収集運搬を行っている企業です。全国47都道府県の幅広い地域からPCB廃棄物の引き取りに対応し、特に少量保管事業者のニーズに応じて、複数の荷主の廃棄物を混載することで運搬コストの低減を実現している点が強みです。
さらに、作業に従事するスタッフは全員がPCB作業従事者講習を修了しており、GPSによる運搬ルートの管理や10億円規模の保険加入など、安全性の確保にも注力。
| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
| 電話番号 | 054-366-1312 |
| 公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
また、書類作成から収集・運搬までをワンストップで提供しており、すでに約5,000件を超える実績を持っています。環境負荷低減の面でも、低燃費車両の導入やルート最適化など、SDGsを意識した取り組みを進めています。
丸両自動車運送株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇DOWAエコシステム株式会社

DOWAエコシステム株式会社は、DOWAホールディングスグループに属する総合的な環境・リサイクル企業です。産業廃棄物の収集運搬から中間処理、そして最終処分までを自社グループ内で一貫して行う体制を整えています。
特にPCB廃棄物の処理においては、長年培ってきた技術力と高度な専用設備により、安全かつ確実な処理を実施しています。岡山、秋田、千葉など全国にPCB処分施設や運搬ネットワークを有し、収集から無害化処理までワンストップで対応可能。
| 会社名 | DOWAエコシステム株式会社 |
| 所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 |
| 電話番号 | 0800-222-5374 |
| 公式ホームページ | https://www.dowa-pcb.jp/ |
環境保全と資源循環型社会の構築に貢献することを企業理念とし、PCBを含む有害廃棄物の処理分野において業界内でも高い評価を受けています。
DOWAエコシステム株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼キュービクルにPCB産業廃棄物が含有されていたらどうすればよい?処分方法を解説
◇株式会社 新関西テクニカ

株式会社新関西テクニカは、京都府に本社を構える産業廃棄物の収集運搬・処理企業です。
同社は関西地域を中心に事業を展開しており、自治体から「優良産廃処理業者」として認定されている点が大きな特徴です。この認定は法令遵守や環境への配慮、事業の透明性や健全な財務体質などが審査されるもので、信頼性の高い事業運営が行われていることを示しています。
| 会社名 | 株式会社 新関西テクニカ |
| 所在地 | 〒611-0031 京都府宇治市広野町新成田100-177 |
| 電話番号 | 0774-43-2380 |
| 公式ホームページ | https://kanteku.co.jp/ |
PCB廃棄物処理事業においては、収集運搬から処理までを自社で一貫して行う体制により、無駄のない対応とコストの最適化が強みです。PCB廃棄物処理の対応エリアは、京都・大阪・滋賀・奈良・兵庫・三重など関西を中心に幅広く対応しています。
こちらも併せてご覧ください。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)汚染物は、その高い毒性から人体や環境に深刻な害をもたらすため、多くの国や地域で製造や輸入が厳しく制限され、禁止されています。この汚染物は主に以下の3種類があり、それぞれ適切な処理方法が必要です。感圧複写紙、ウエス(繊維くず)、汚泥が該当します。
PCB汚染物の回収が始まった背景には、カネミ油症事件が重要な要因であり、この事件がPCBの危険性を浮き彫りにしました。その後、JESCOなどを活用して国内に処理施設を整備し、持続的な環境汚染を防ぐための取り組みが進められました。
PCBの該当性判断基準は対象物によって異なり、含有量に基づいて処理方法が設定されています。また、適切な分析方法を用いてPCBを正確に測定する必要があります。分析方法は洗浄液試験法、抜き取り試験法、部材採取試験法の3種類があり、対象物に応じて選択されます。これらの規制と分析方法はPCB汚染物の安全な処理と環境保護のために重要です。
この記事を読んでいる人におすすめ