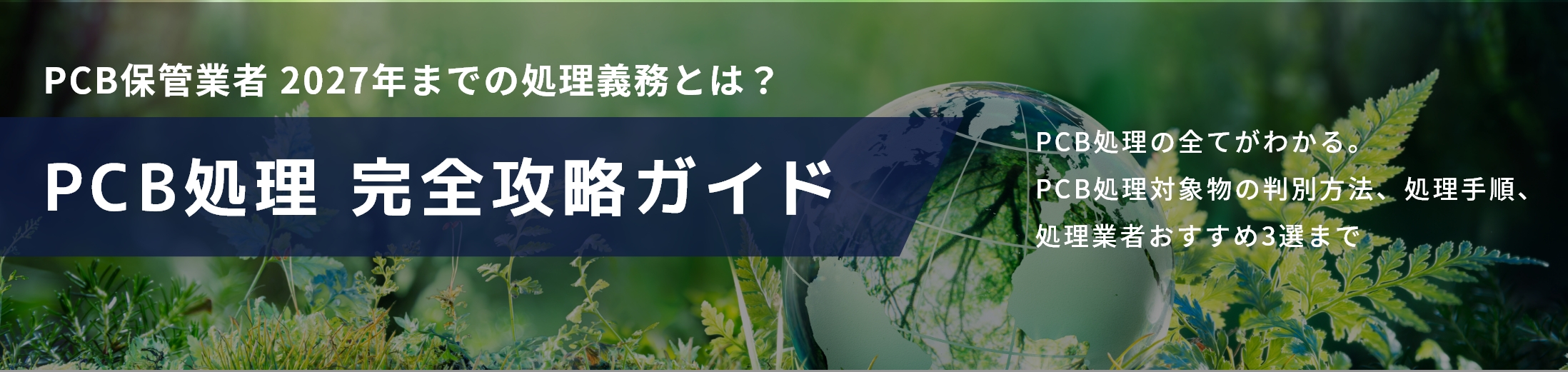低濃度PCB廃棄物は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)濃度が0.00005%から0.5%以下の廃棄物を指します。廃油や汚染物、処理物などの種類があり、その特性によって適切な処理が求められます。製造年やメンテナンス履歴を確認し、PCB濃度を測定することで見分けることが可能です。
目次
低濃度PCB廃棄物とは?PCB廃棄物の区分

PCB廃棄物は、その濃度によっていくつかの区分に分けられます。その中でも、低濃度PCB廃棄物は、PCB濃度が0.00005%を超え0.5%以下の廃棄物を指し、1972年以前に製造された機器だけでなく、それ以降の製品にも含まれる可能性があります。
◇高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の違い
高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)の濃度に基づいて区分されます。高濃度PCB廃棄物は、PCB濃度が0.5%を超えるものであり、通常は特定の電気工作物から得られます。このような電気工作物には、昔の高圧変圧器や高圧コンデンサーなどが含まれます。一方、低濃度PCB廃棄物は、PCB濃度が0.00005%から0.5%以下のものです。これは、再生絶縁油を含む電気機器から発生します。
高濃度PCB廃棄物は、その処理については専門の機関である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で行われます。一方、低濃度PCB廃棄物は、その存在量が多いため、地域の無害化処理認定施設や都道府県の許可を得た民間の施設で処理されます。
◇低濃度PCB廃棄物とは

低濃度PCB廃棄物とは、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む廃棄物のうち、PCB濃度が0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下の範囲にあるものです。具体的には、PCBを含んだ絶縁油や、それが付着した汚染物、さらにPCB汚染が広がった廃電気機器などが該当します。
また、塗膜くずや感圧複写紙などの可燃性PCB汚染物については、PCB濃度が100,000mg/kg(10%)以下のものが低濃度PCB廃棄物に当たります。
低濃度PCB廃棄物は、PCBの含有量が比較的少ないとはいえ、依然として人体や環境に有害であり、その処理には厳格な管理が求められます。処理は法的に厳しく規制されており、適切な方法で対応することが非常に重要です。
なお、低濃度PCB廃棄物は、より具体的には「微量PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等)」と「低濃度PCB含有廃棄物」に分類されます。微量PCB廃棄物の詳細については、後述します。
【あわせて読みたい】
▼低濃度PCB産業廃棄物なら処理も可能!鹿島環境エンジニアリング株式会社の収集運搬サービス
低濃度PCB廃棄物の種類
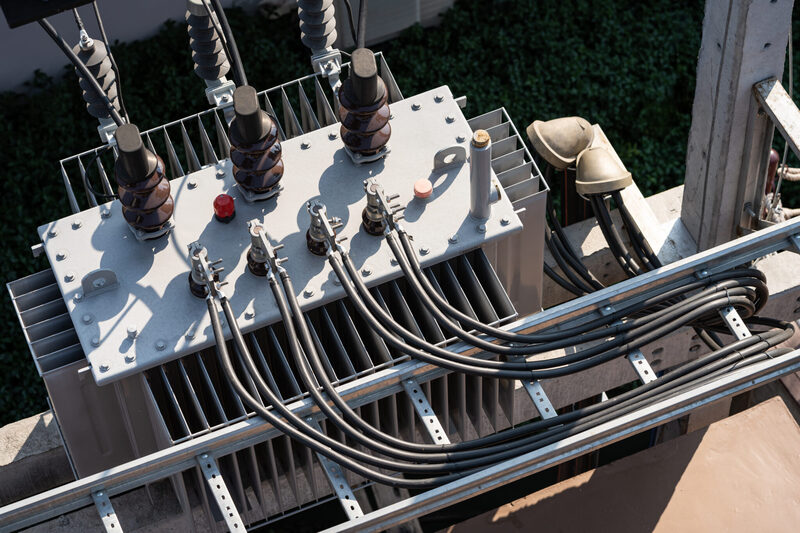
低濃度PCB廃棄物は、環境への影響が比較的少ない廃棄物でありながら、その構成や性質によってさまざまな種類が存在します。これらの種類には、廃油、汚染物、処理物などが含まれ、それぞれが異なる処理方法や管理手順を必要とします。
◇低濃度PCB廃油
低濃度PCB廃油は、PCB濃度が1kgあたり5,000mg以下の液状の廃油を指します。主に微量PCB汚染絶縁油や低濃度PCB含有廃油がこれに該当し、電気機器やOFケーブルから抽出される絶縁油や潤滑油がこれに含まれます。
◇低濃度PCB汚染物

微量PCB汚染絶縁油が染み込んでいたり、付着したりしているものや、封入されたものも廃棄物として取り扱われます。
100,000mg/kg以下のPCB濃度の汚泥、紙や木材、布などのくず類、廃プラスチック類。
PCB濃度が5,000mg/kg以下の金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物に付着したもので、主に固形であることがほとんどです。
◇低濃度PCB処理物
低濃度PCB処理物は、PCB濃度が1kgあたり5,000mg以下の廃棄物を処理した結果得られた物を指します。主に微量PCB処理物や低濃度PCB含有処理物がこれに該当し、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃泥、紙くず、木くず、廃プラスチック類、金属くずなどが含まれます。廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づく無害化処理が行われます。これらの廃棄物は、種類ごとに処理方法が異なりますが、いずれも適切な管理が必要です。
【あわせて読みたい】
▼まだ間に合う!今からでも活用できる低濃度PCB廃棄物処理支援事業の補助金
微量PCB廃棄物

PCBはその有害性から禁止されましたが、現在もさまざまな機器や設備に微量が含まれていることが確認されています。以下では、微量PCB廃棄物が発見された経緯を振り返り、廃棄物の種類やその区分について詳しく解説します。
◇微量PCB廃棄物とは
微量PCB廃棄物とは、本来PCBを使用していない機器や物質に意図せずPCBが混入したものであり、なおかつPCB濃度が0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下の範囲にある廃棄物を指します。
微量PCB廃棄物は、PCBを使用した他の電気機器と比べてその含有量が少ないとはいえ、依然として環境や人体に有害であるため、適切な処理が求められます。特に、絶縁油やそれに付着した汚染物、またはPCBが混入した電気機器などが含まれ、PCBの漏洩や流出を防ぐための処理が求められます。
◇微量PCBが発見された経緯

PCBの製造と使用は1972年に禁止されましたが、その後も微量のPCBを含む機器が発見され、問題となっています。特に2002年には、PCBを使用していないとされる電気機器にも数十ppmのPCBが混入した絶縁油が含まれていることが明らかになり、社会的な関心を呼びました。
この混入の原因を調査するため、「微量PCB検出変圧器等対策委員会」が結成され、本格的な調査が始まりました。この委員会には25社以上の企業が参加しています。委員会では、製造過程でのPCBの混入や納入後に発生した汚染、さらには絶縁油へのPCB混入の可能性について徹底的に調査しました。
その結果、1972年以前、多くの企業でPCBの有害性に対する認識や理解が不十分であったため、その下で広く製造が行われていたことが明らかになりました。つまり、当時は絶縁油や再生油の取り扱いに関する知識が不十分であり、そのためPCBが意図せず混入するリスクが高かったのです。
さらに、1990年までの間、再生原料として使用される油(元油)はPCBを含まないと考えられていたため、再生利用が頻繁に行われていました。もし再生原料にPCBが含まれていた場合、この再生利用によって微量のPCBが広がる原因となった可能性があります。
◇微量PCB廃棄物の種類

微量PCB廃棄物は、かつて絶縁油などに使用されたPCB(ポリ塩化ビフェニル)が微量ながら残留している廃棄物であり、厳格な管理と適切な処理が求められます。ここでは、主に3つに分類される微量PCB廃棄物の種類について解説します。
・微量PCB汚染廃油
微量PCB汚染廃油とは、本来PCBを使用していないはずの電気機器やOFケーブルなどに使われた絶縁油が、微量のPCBによって汚染され、廃棄物となったものです。
この絶縁油は、もともとPCBを主成分とするものではないため、見た目では判断しづらいものの、微量でもPCBが含まれている場合は環境負荷の高い特定廃棄物として分類され、厳格な管理のもとで処理しなければなりません。
特に旧型の変圧器やケーブル設備の絶縁油には、製造過程や経年劣化によりPCBが混入しているケースがあるため、注意深い取り扱いが求められます。
・微量PCB汚染物
微量PCB汚染物とは、微量PCBに汚染された絶縁油が、機器や材料に塗布・浸透・付着・封入された結果、PCB汚染物として分類される廃棄物です。これには、絶縁油が染み込んだ紙類や布、構造材、ゴム、樹脂部品などが含まれます。
外観上、汚染の有無が分からないことが多く、現場での初期判断が難しいことが特徴です。そのため、微量PCBの可能性があるものについては、専門機関による分析や記録の確認を通じて、適切に「PCB汚染物」として取り扱う必要があります。
・微量PCB処理物
微量PCB処理物とは、微量PCB汚染廃油や微量PCB汚染物など、PCBが微量ながら含まれていた廃棄物を適正に処理した結果生じた処理済みの廃棄物です。焼却や脱塩素化処理など、PCBを分解・無害化する方法によって処分され、その後に残ったものが「微量PCB処理物」として区分されます。
これらはすでに有害性を除去したものですが、処理の履歴や処分工程が明確に管理されていることが求められます。また、処理後であっても最終的な保管や埋立てにおいて法的な管理が継続される場合があり、処理物としての扱いにも高い透明性と責任が伴います。
微量PCBの処理は、単なる廃棄ではなく、環境への影響を最小限に抑えるための重要な措置として位置づけられています。
◇低濃度PCB廃棄物の区分

| 低濃度PCB廃棄物 | 該当する主な廃棄物 | |
| 低濃度PCB廃油 | 微量PCB汚染絶縁油 | 電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの |
| 低濃度PCB含有廃油 | PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃油等 | |
| 低濃度PCB汚染物 | 微量PCB汚染物 | 微量PCB汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、または封入されたもの |
| 低濃度PCB含有汚染物 | 汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類に付着した、PCB濃度が100,000mg/kg以下のもの。金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物に付着した、PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの | |
| 低濃度PCB処理物 | 微量PCB処理物 | 低濃度PCB廃油および低濃度PCB汚染物を処分するために処理したもの |
| 低濃度PCB含有処理物 | PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの |
【あわせて読みたい】
▼政府が低濃度PCB廃棄物の処理促進を促す理由は?取り組みを紹介
低濃度PCB廃棄物の見分け方

ここでは、低濃度PCB廃棄物が含まれているかどうかの、見分け方を解説します。
◇低濃度PCB廃棄物の見分け方
国内メーカー製で、平成2年(1990年)以前に製造した電気機器の、絶縁油の入替ができないタイプは低濃度PCBが含まれていると考えられます。
平成6年(1994年)以降の製造でなおかつ、絶縁油の交換等のメンテナンス歴がない場合は、PCB汚染のリスクは低いと考えられます。
◇安定器・コンデンサ・変圧器の場合

まず、安定器にPCBが含まれるかは、製造年月から判別します。昭和32年(1957年)から昭和47年(1972年)までの安定器や、昭和52年(1977年)までの建築・改修した建物には、PCBを含む安定器が使用されている可能性があります。ただし、一般家庭用の蛍光灯の安定器にはPCBは含まれていません。
コンデンサの絶縁油が入れ替えできない場合や、1991年より以前に製造されたコンデンサは、PCB濃度を測定して判別をしますが、使用中のコンデンサを穿孔すると使用不能になるため、気を付けるようにしましょう。
変圧器は絶縁油の入れ替えが可能なため、汚染の可能性は製造年やメンテナンス実施履歴によって判断するのが一般的です。平成6年(1994年)以降の製品で、メンテナンス歴がない場合はPCB汚染のリスクは低いと考えられます。
◇汚染物等の場合
汚染物が低濃度PCB廃棄物かどうかを見分けるには、含まれるPCBの濃度を測定する必要があります。汚染物から採取した試料を特定の方法で測定し、PCBが検出された場合は、その物質は特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物となります。一方、測定結果によってPCBが検出されない場合は、その物質は低濃度PCB廃棄物ではなく、通常の産業廃棄物として分類されます。
【あわせて読みたい】
▼使用中の低濃度PCB製品の取り扱いと廃棄期間とは?専門業者の選び方
微量PCB廃棄物の見分け方

PCBは微量であっても有害性が高く、適切な管理と処理が求められます。ここでは、微量PCBが混入している可能性のある電気機器の範囲や、使用後に行うべき確認・分析の手順、そして実際の処理方法について、基本的なポイントを解説します。
◇混入の可能性がある電気機器
微量PCBについて、絶縁油の混入可能性を理解するためには、過去の取り組みと現在の状況を踏まえることが重要です。2005年に実施されたPCB汚染物対策検討委員会の報告によると、1990年2月以降に製造された新しい絶縁油には、製造過程でPCBが混入する可能性はないとされています。
しかし、電気機器を含めすべての製品が完全に安全であるわけではなく、いくつかのメーカーからは「一部のコンデンサに微量のPCBが検出された」や「微量PCBの混入の可能性を完全に排除できない」といった声明も出されています。
これにより、PCBが混入していない絶縁油と、微量の混入の可能性が残る絶縁油が存在することが示唆されています。そのため、現在も絶縁油の安全性を確認するための検査や確認作業が重要です。
◇1990年以降に製造されたものについても例外がある

1990年以降に製造された製品に関しても、すべてが完全に安全であるとは限らないという点に留意が必要です。先に述べたように、一部のメーカーは1990年以降に製造された製品でもPCBの混入の可能性を完全に否定できないとしており、これらのメーカーは例外として扱う必要があります。
具体的には、以下のメーカーが自社の製品に関するPCB混入についてホームページで声明を発表しています。
・ニチコン
1990年以降に製造された一部のコンデンサにおいて、微量のPCBが検出されています。
・東芝
「1990年以降に販売された一部の高圧コンデンサにおいて、微量PCBの混入の可能性が完全に否定できない」と公式に発表しています。
・富士電機
1989年以前に購入した新油の絶縁油が封入されている機器が存在することを説明しています。
◇微量PCB廃棄物の確認方法と分析の必要性

微量PCBを含む可能性のある廃電気機器を適切に処理するためには、製造元に問い合わせて、当該製品が微量PCBに汚染されている可能性があるかどうかを確認する必要があります。製造時期や構造により、外観だけでは判断できない場合も多いため、製造者の情報が判断の手がかりとなります。
特に、変圧器などの絶縁油を使用している機器については、微量PCBの混入が完全に否定できないとされるタイプが多く存在します。そのような機器については、使用を終えた段階で速やかに絶縁油の分析を行い、PCBの有無を確認することが重要です。
分析にあたっては、厚生労働省が公開している「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」を参考にすることができます。特に「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」が公表されており、正確かつ効率的にPCBの有無を判定することが可能です。
◇微量PCBの処理について
微量PCBが含まれている廃電気機器は、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の処理対象には含まれません。そのため、これらの廃棄物を適切に処理するためには、都道府県から許可を受けている、または環境省によって認定された専門の処理事業者に依頼する必要があります。
微量PCBの処理方法には、従来からある高温焼却や化学分解といった方法のほか、近年注目されている「課電自然循環洗浄法」があります。この方法は、対象となる機器に電圧をかけた状態で、専用の洗浄液を内部に循環させることにより、残留するPCBを徐々に溶出・除去する技術です。
この課電自然循環洗浄法に関しては、経済産業省と環境省が共同で「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」を公表しており、処理を行う際にはこの手順書に基づいた対応が求められます。
【あわせて読みたい】
低濃度PCB廃棄物の処分について

つぎに、低濃度廃棄物と判別された場合は、産業廃棄物処理法に基づいて処理する必要があります。
◇届出を行う
PCBを処理する際は、PCB特別措置法に基づき、PCB廃棄物を保管している事業所を管轄する環境管理事務所に、届出が必要です。届出の方法や低濃度PCB廃棄物の処理期限などは、自治体によって異なります。
PCBをどのように所有しているのかの状況により、記載する様式が違いますので事前に確認しましょう。
◇使用中の電気機器の場合
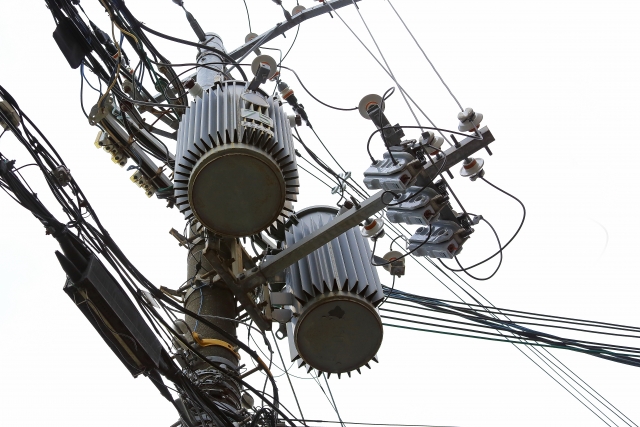
現在使用している電気機器が微量(低濃度)のPCBを含んでいることが判明した場合、必ず所定の手続きを行う必要があります。この場合、「電気事業法」に基づき、機器を設置している地域を担当する産業保安監督部に速やかに届出を行わなければなりません。
また、設置者の氏名や住所、工場や事業場の名称や所在地が変更された場合や、機器を廃止した場合、事故が発生した場合にも、同様に届出が必要です。
◇保管中・廃棄物の場合

すでに使用を終えた電気機器で、微量のPCBを含むものは「低濃度PCB廃棄物」として取り扱われます。これらは「廃棄物処理法」に従い、適切な方法で保管しなければなりません。また、毎年決まった時期に次のような届出が必要です。
具体的には、その年度末までに発生した低濃度PCB廃棄物(まだ保管しているものを含む)や、処分が完了したものの状況を翌年度の6月末までに保管場所のある都道府県または政令指定都市に報告する必要があります。さらに、保管場所を移した場合は10日以内に届出が必要であり、すべての廃棄物の処分が完了したときは、20日以内にその完了を届け出ます。
なお、機器の内部に少量の絶縁油が封入されているコンデンサーや小型の変圧器などを処分する場合、たとえ無害化処理を行ったとしても、年度ごとの届出が必要です。
◇無害化処理認定施設で処理を行う

無害化処理認定制度は、平成18年(2006年)に設けられ、アスベストを含む廃棄物や微量PCB汚染廃家電機器など産業廃棄物の処理に適用される制度で、令和元年(2019年)に改定されました。
この制度は、安全で効率的に融解処理を行うための条件を定めたもので、国内には30ヵ所以上の無害化処理認定制度を取得した施設があります。
ただし、一つの施設で全ての廃棄物を処理できるわけではなく、施設ごとに処理できる廃棄物が異なります。
また、使用中の変圧器に微量のPCBが含まれている場合、その変圧器の構造やPCB濃度、絶縁油の量などによっては、使用しながら浄化する「課電自然循環洗浄法」が適用される場合があります。
【あわせて読みたい】
▼CDP洗浄法とは?新たに認定された低濃度PCB廃棄物の無害化技術
低濃度PCB廃棄物の運搬や処分に対応可能な業者
低濃度PCB廃棄物の運搬や処分には、専門的な知識と設備を持った業者に依頼することが重要です。適切な業者選定により、安全かつ法令に則った処理が可能となり、環境への負担を軽減することができます。以下では、PCB廃棄物に対応可能な信頼できる業者を紹介します。
◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送株式会社は、産業廃棄物全般の収集運搬から処理までを一貫して行う企業で、特にPCB廃棄物の取り扱いにおいて豊富な実績を有しています。現在までに、約5,000件以上のPCB廃棄物処理の経験があり、この分野での信頼性は非常に高いです。
同社の最大の強みは、作業従事者が全員「PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会」を修了しており、高い専門知識と技術を備えている点です。PCB廃棄物処理には法的な規制が多く、専門的な取り扱いが求められますが、丸両自動車運送株式会社はこの点においても安心です。
| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
| 電話番号 | 054-366-1312 |
| 公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
また、運搬中にはGPSを活用し、経路や位置の確認を行っているのも同社の特徴です。さらに、万が一の事故に備えて最大10億円の保険にも加入しています。
丸両自動車運送株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇光和精鉱株式会社

光和精鉱株式会社は、製鉄用ペレットの製造を中心に事業を展開している企業ですが、廃棄物処理分野にも力を入れており、特にPCB廃棄物の無害化処理において国内での先駆者的存在です。同社は2010年に国内で初めて、低濃度PCB汚染廃電気機器の無害化処理認定を受けました。
光和精鉱のPCB廃棄物処理の特徴は、処理過程の透明性を高めるために情報公開ルーム設置していることです。このルームでは、処理状況や環境モニタリング値などがリアルタイムで公開されており、顧客は処理過程をモニタリングすることができます。
| 会社名 | 光和精鉱株式会社 |
| 所在地 | 〒804-0002 福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46-93 |
| 電話番号 | 0120-582-380 |
| 公式ホームページ | https://www.kowa-seiko.co.jp/ |
さらに、環境保護の観点からも配慮されており、処理が完了するまでの全過程で厳密な環境管理が行われています。
光和精鉱株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼光和精鉱のPCB廃棄物処理~総合技術と全国の代理店ネットワーク
◇三重中央開発株式会社

三重中央開発株式会社は、収集・運搬から中間処理、再資源化、最終処分までを一貫して手掛ける企業です。同社のPCB廃棄物の処理に特に注目すべきは、ジオメルト法と呼ばれる溶融焼却技術を採用している点です。
この技術は、1,200℃から2,000℃の高温でPCBを溶融させ、完全に無害化することができます。PCBは非常に難処理物質であり、適切な技術を用いなければ処理が困難ですが、ジオメルト法はその問題を解決し、処理後の廃棄物が環境に与える影響を最小限に抑えることができます。
| 会社名 | 三重中央開発株式会社 |
| 所在地 | 〒518-1152 三重県伊賀市予野字鉢屋4713 |
| 電話番号 | 0595-24-5111 |
| 公式ホームページ | https://miechuokaihatsu.jp/ |
三重中央開発株式会社のジオメルト無害化施設は、1日あたり約4.75トンのPCB廃棄物を処理できる能力を誇り、大規模な処理にも対応可能です。
三重中央開発株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
PCB廃棄物は、その濃度に応じて高濃度と低濃度に分類されます。低濃度PCB廃棄物は、PCB濃度が0.00005%から0.5%以下のものを指し、主に再生絶縁油を含む電気機器から発生します。このカテゴリーには、微量PCB汚染廃電気機器も含まれ、特に1990年以前の製品に頻繁に見られます。低濃度PCB廃棄物は、廃油、汚染物、処理物などの種類があり、それぞれが適切な処理を必要とします。
低濃度PCB廃棄物を見分けるには、製造年やメンテナンス履歴を確認し、必要に応じてPCB濃度を測定することが重要です。処理方法としては、まず環境管理事務所に届出を行い、その後は無害化処理認定施設を利用することが一般的です。
このような取り扱いが必要な理由は、低濃度PCB廃棄物が環境への影響が少ないとはいえ、適切な管理が不十分な場合には環境や人間の健康への悪影響が懸念されるためです。そのため、処理や廃棄の際には、法的規制に基づいた適切な手続きを踏むことが重要です。
この記事を読んでいる人におすすめ