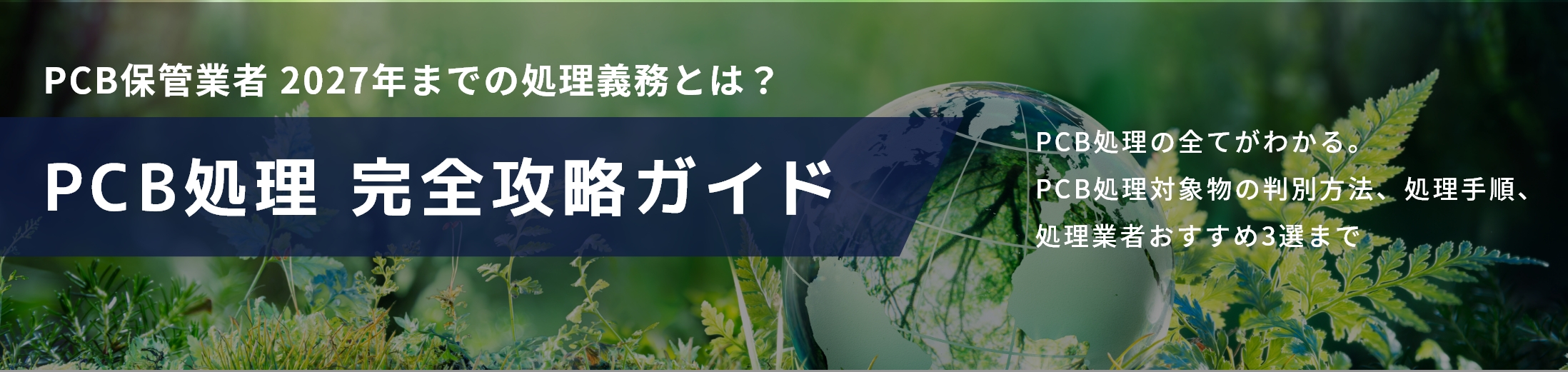DDTはかつて「万能の殺虫剤」として広く利用され、農業や感染症対策において重要な役割を果たしました。しかし、その強力な効果の裏には、環境や生態系への深刻な影響が隠されており、1960年代以降、その有害性が指摘されるようになりました。現在では多くの国で使用が制限されているものの、発展途上国においては依然として感染症予防に使用されています。
目次
殺虫剤などで広く使用されたDDT

DDTは殺虫剤や農薬として、かつて日本を含む世界各国で広く使用されました。DDTとはどのようなもので、なぜ広く使用されたのでしょうか?DDTの歴史や特徴をご紹介します。
◇DDTとは

DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)は、有機塩素系殺虫剤の一つで、その名称は英語の「Dichloro Diphenyl Trichloroethane」の頭文字を取ったものです。
この化合物は1873年にドイツの化学者オーストによって初めて合成されました。その高い殺虫効果が発見されたのは1939年、スイスの化学者パウル・ヘルマン・ミュラー博士の研究によるものでした。
この功績により、ミュラー博士は1948年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。この発見は殺虫剤分野に画期的な進展をもたらし、DDTは「夢の殺虫剤」として広く普及しました。
・DDTの特徴と利用拡大
DDTは、多様な害虫に対して極めて高い効果を発揮します。蚊やハエ、ノミ、アブラムシといった病害虫だけでなく、農業分野では収穫を脅かすさまざまな害虫の駆除にも利用されました。
その強みは、安価で大量生産が可能であること、そして人間や哺乳類など高等生物に対する急性毒性が比較的低いことです。特に第二次世界大戦中と戦後の時代、DDTはマラリアや発疹チフスなどの感染症対策で絶大な効果を発揮しました。こうした実績から、「公衆衛生の救世主」として称賛されました。
・環境への影響と規制
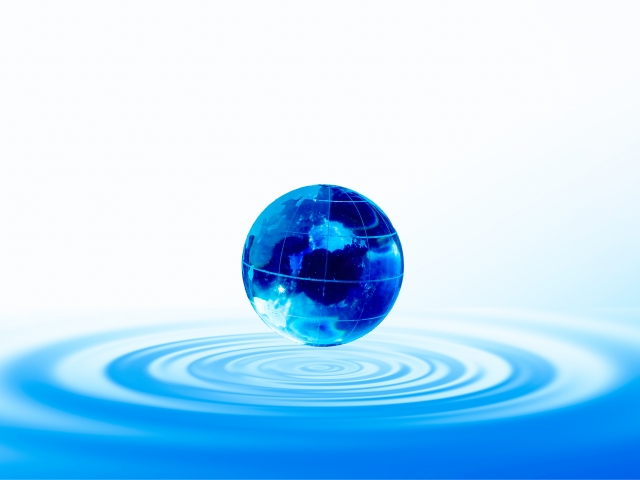
しかし、DDTの環境への影響が次第に問題視されるようになりました。DDTは分解されにくい性質を持ち、環境中に長期間残留します。さらに、食物連鎖を通じて生物の体内に蓄積される「残留性有機汚染物質(POPs)」として注目されました。
特に鳥類では、卵殻が薄くなり繁殖率が低下するなどの深刻な生態系への影響が確認されています。このため、1970年代以降、多くの先進国でDDTの使用が禁止または厳しく制限されるようになりました。
・発展途上国での限定的な利用

一方で、蚊を媒介とするマラリアやデング熱などの感染症が深刻な地域では、DDTの使用が続いています。世界保健機関(WHO)は、感染症流行地域における室内残留噴霧(IRS)という限定的な用途に限りDDTの使用を認めています。このように、現在のDDTは主要な農薬としての役割を終えたものの、防疫手段としての重要性は続いています。
・現在の生産と今後の課題
現在、DDTは主に中国やインドで生産されています。これらの国々では、感染症対策を目的とした需要に応えるため、生産と供給が続けられています。一方で、環境保護や健康リスクの懸念が引き続き課題となっています。
DDTはかつて「奇跡の化学物質」として世界中で広く利用されましたが、その環境負荷と生態系への影響が明らかになるにつれ、使用に関する考え方が大きく変わりました。それでもなお、発展途上国における公衆衛生の改善においては、重要な役割を果たし続けています。この複雑な背景を持つ化学物質は、科学技術の進展とともに、環境保護と人類の健康のバランスを問い直す象徴的な存在です。
◇かつて広く使用されていたDDT

DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)は、安価で大量生産が可能なうえ、蚊やシラミ、ノミなどの害虫に対して強力な効果を持ち、人間など高等生物への急性毒性が比較的低いことから、「夢の化学物質」「万能の殺虫剤」と称されました。
そのため、食糧増産や感染症撲滅の切り札として、世界中で積極的に利用されました。DDTの使用は1939年にスイスのミュラー博士が殺虫効果を発見したことから本格化し、第二次世界大戦中にはイギリスとアメリカが工業的な生産体制を確立。
戦地でのマラリアや発疹チフスなどの感染症対策として、兵士や民間人の衛生管理に大きく貢献しました。
日本においては、戦後間もない1946年に連合国軍総司令部(GHQ)によってDDTが持ち込まれ、まずはシラミ駆除を目的として全国的な防疫活動に利用されました。これにより、戦後の日本を悩ませていた発疹チフスやその他の伝染病の流行が急速に抑え込まれ、衛生状態の劇的な改善に寄与しました。
その後、1950年代に入ると、DDTは農業分野でも広く普及し、稲や果樹、野菜など多様な作物の害虫防除に用いられるようになりました。特に、戦後の食糧増産政策と相まって、農業現場では「万能の農薬」として重宝され、短期間で全国に普及しました。
世界的にも、DDTの使用は爆発的に拡大し、使用開始からわずか30年で累計300万トン以上が消費されたとされます。安価で効果が高く、即効性があることから、発展途上国でも感染症対策や農業生産の向上に大きく貢献しました。
こうした背景から、DDTは20世紀中盤の公衆衛生・農業技術の象徴的な存在となりました。
【あわせて読みたい】
▼PCBなど有害物質を含む産業廃棄物処理の難しさと日本の対策とは?
DDTの人体や生態系への影響と危険性

画像出典:photoAC
1962年にレイチェル・カーソンが出版した「沈黙の春」は、アメリカにおいてベストセラーとなりました。その中では、DDTが生態系や人体に与えうる悪影響が詳細に指摘されていました。
◇生態系への影響

DDTは強力な殺虫効果があるぶん、受粉を手助けするミツバチのような、人間にとっての益虫も殺してしまう可能性があります。また、レイチェル・カーソンは「沈黙の春」において、DDTは油に溶けやすく分解されにくいこと、食物連鎖の過程で濃縮されていくことを指摘しました。
実際に、害虫駆除のためDDTに似た物質が散布されたアメリカの湖において、カイツブリという鳥が大量死したことが知られています。DDTの影響は、神経系や肝臓、ホルモン分泌組織、生殖、胎児の発育、免疫系など広範囲に及ぶとされ、動物実験では肝臓での腫瘍形成も確認されました。
◇人体への影響
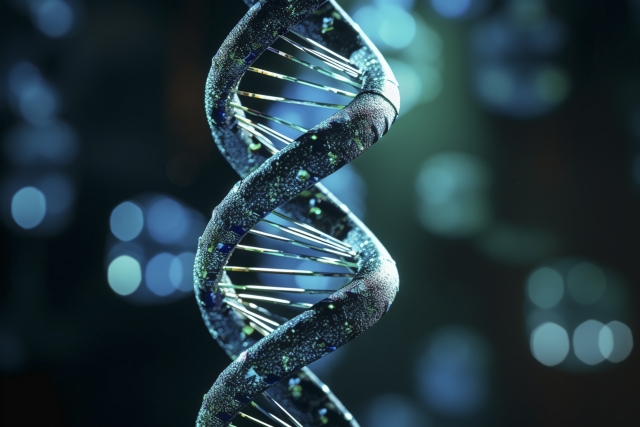
先ほど解説したとおり、DDTは油に溶けやすいうえ分解されにくく、食物連鎖の過程で濃縮されていきます。プランクトンから魚、魚から鳥、というように高等生物になるほど濃縮され、私たち人間が普段口にする家畜や魚に蓄積されるのはもちろん、ミルクや卵にも移行します。
哺乳類や鳥類への急性毒性は低いとされているものの、動物実験の結果などから、人間に対しての悪影響は否定できません。1970年代の母乳からは現在の10倍以上のDDT類が検出されたとする報告、DDTと男性の生殖器異常の関連を示唆する報告も上がっています。
DDTの使用制限と代用品の開発

レイチェル・カーソンの指摘以降、DDTはその悪影響が広く認知され、使用や製造が厳しく制限されるようになりました。
◇日本では使用禁止
アメリカでは、1972年に環境保護の観点から使用が制限され、やがてDDTを含む有機塩素系農薬の生産量が全盛期の三分の一以下まで減少しました。その有害性は他国でも広く認識され、2000年までに先進国を中心に40以上の国で使用が禁止・制限されています。
2001年には、「残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約」において、産業廃棄物に含まれるPCBなどと同様に、全世界における製造や使用の制限が採択されました。
日本でも、1971年に「農薬取締法」においてDDTの販売が禁止され、1981年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」において製造・輸入が禁止されました。
◇DDTに変わる農薬の開発

DDTの製造・販売が禁止された後、日本では新たな農薬が次々と開発され、それぞれの特徴を活かしつつも課題を克服する努力が続けられてきました。有機リン剤、合成ピレスロイド系、成長抑制剤(IGR剤)、ネオニコチノイド系の農薬が現在の主流となり、以下のような特徴があります。
・有機リン剤
有機リン剤は、DDTと同時期に普及した殺虫剤の一つで、初期には毒性の高さが問題となりました。特に農作業中の中毒事故が多発し、改善が求められました。その結果、より毒性が低い「マラソン」や「ダイアジノン」といった製品が開発され、現在でも広く使用されています。
これらの改良型有機リン剤は、接触作用や吸収作用により害虫を効率的に駆除する特徴がありますが、使用時には適切な管理が必要です。
・合成ピレスロイド系
合成ピレスロイド系は、除虫菊に含まれる天然成分を基に開発された農薬で、多様な昆虫に少量で強力に作用します。この特性から、多くの家庭用・農業用殺虫剤に利用されています。しかしながら、以下の課題が挙げられます。
- 魚類への毒性: 魚類に対しては高い毒性を示すため、水田や水辺での使用には注意が必要です。
- 耐性問題: 昆虫が短期間で耐性を獲得しやすい点が課題とされています。
これらのデメリットに対応するため、特定の環境で使用を制限したり、耐性発生を遅らせる使用方法が推奨されています。
・成長抑制剤(IGR剤)
成長抑制剤は、昆虫の成長に不可欠なホルモンや物質の働きを阻害することで駆除効果を発揮します。この仕組みの特長は以下の通りです。
- 耐性問題への対応: 従来の殺虫剤に耐性を持つ害虫にも高い効果を示します。
- 非標的生物への影響軽減: 昆虫以外の生物への影響が少ないため、環境負荷が比較的低いと評価されています。
これらの特性により、成長抑制剤は現在の環境に配慮した農薬として注目されています。
・ネオニコチノイド系
ネオニコチノイド系農薬は、タバコの葉に含まれるニコチンの成分を基に開発されたものです。戦前から天然由来の殺虫剤として利用されていましたが、広範囲の生物に影響を及ぼす問題がありました。近年では、以下の改善が行われています。
- 特定標的への効果向上: 特有の分子構造を活用し、駆除対象の昆虫に限定した作用を持つ製品が開発されました。
- 持続性の強化: 長期間安定した効果を発揮し、使用頻度を減らすことが可能となりました。
ネオニコチノイド系は、高い効率性と環境への影響の軽減を両立させる現代農薬の代表格として、家庭用から商業農業まで幅広く使用されています。
これらの農薬は、環境や健康への影響を軽減する工夫が続けられ、用途や目的に応じて使い分けられています。一方で、それぞれの特性や課題を十分に理解し、適切な使用方法を守ることが求められます。
持続可能な農業を実現するために、これらの農薬の選択と管理は今後も重要な課題であり続けるでしょう。
【あわせて読みたい】
DDTの上手な活用が求められる

DDTは生態系や人体に与えうる悪影響から、世界的に禁止・制限されることとなりました。しかし、未だDDTに代わる成分は開発されておらず、その有用性から上手な活用が求められています。
◇感染症撲滅に確かな功績
マラリアは、HIV・結核と共に「世界三大感染症」と呼ばれ、年間3~5億人が感染し、150~270万人が死亡していると推測されています。アフリカやアジア、南太平洋諸国、中南米など95の国や地域で確認されており、死亡者の93%はサハラ以南のアフリカ、特に5歳未満の子どもに集中しています。
DDTは、マラリアを媒介する蚊を駆除することで、多くの人命を救ってきました。DDTによって救われた人命は、5000万人とも一億人とも言われ、1948年には、効能の発見者であるパウル・ヘルマン・ミュラー博士がその功績を称えられ、ノーベル生理学・医学賞も受賞しました。
DDTの功績は戦後日本においても大きく、発疹チフスにより200万人が死亡すると予想されていたものの、シラミの駆除によりそのほとんどが救われています。
◇使用禁止による影響
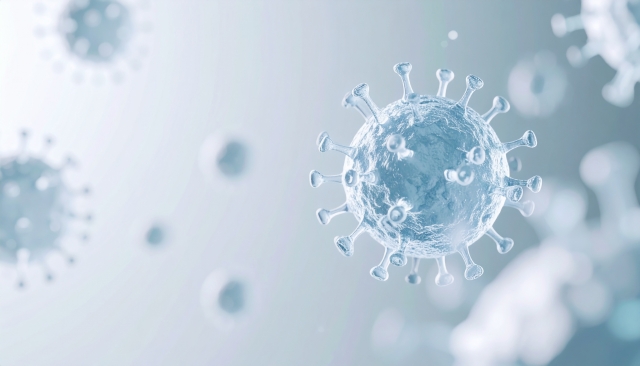
スリランカでは、1948~1962年にかけてのDDTの定期散布により、年間250万人にも上るマラリアの感染者が、31人にまで激減しました。しかし、DDTの使用禁止以降、僅か5年程で元に戻ってしまっています。南アフリカや中南米の途上国においても、同じような事例が多く確認されました。
◇DDTが未だに必要とされている
人類はDDTに代わるより安全な成分を探し続けてきましたが、同様の効果を持ち安価に大量生産できるものは未だ見つかっていません。
実際に、2001年の「残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約」においても、「疫病を防止するため、かつ代替品がない場合のみ、WHOの指示に基づいて使用を許可する」という条項が加えられています。
これに基づいて、2006年には、WHOが「マラリアとDDTのリスクを比較して、マラリアのリスクが上回る場合のみ使用を許可する」という指示を出しました。WHOは少量のDDTを家の壁などに吹き付けるやり方を勧めており、それを守れば環境への悪影響を抑えてマラリアを予防できるとしています。
DDTが海外から日本に入り込む可能性――現状とリスク、そして対策

DDTはかつて広く使用された殺虫剤ですが、その有害性から日本では完全に禁止されています。一方、海外での使用は続いており、輸入食品や環境汚染を介したリスクが懸念されています。
アフリカやアジア、中南米などの発展途上国では、今なおマラリア対策などの公衆衛生目的でDDTの使用が認められており、主に中国やインドで製造が続けられています。そのため、世界的にはDDTの完全な根絶には至っていません。
このような状況下、日本においてもDDTが「海外から入り込む」可能性はゼロではありません。具体的なリスクとしては、以下のような経路が考えられます。
◇輸入食品や農産物を介した混入

日本は多くの農産物や加工食品を海外から輸入しています。DDTが使用されている国で生産された農産物や食品に、DDTやその分解産物(DDE、DDD)が残留している場合、それが日本国内に持ち込まれるリスクが存在します。
実際、食品衛生法に基づき、DDTの残留基準値が厳しく設定されており、輸入時の検査で基準値を超える場合は流通が認められません。
◇非合法な持ち込みや密輸

DDTは安価で効果が高いため、農業現場などで「効果的な殺虫剤」として違法に持ち込まれるリスクも否定できません。
過去には、海外からの密輸やインターネットを通じた違法な入手が問題となった事例もあります。日本の法令では、DDTの輸入・所持・使用は厳しく禁じられており、違反した場合は厳しい罰則が科されます。
◇国際的な物流・環境汚染を通じた拡散
DDTは環境中で非常に分解されにくく、長期間残留します。国際物流や大気・水流を介して、海外で使用されたDDTが微量ながら日本の環境中に拡散・蓄積される可能性もあります。
特に海洋生物や渡り鳥などを通じて、食物連鎖の上位にある日本国内の生物や人間に蓄積されるリスクが指摘されています。
◇現在の監視体制と対策

日本では、食品衛生法や化学物質審査規制法に基づき、DDTの残留基準値が厳格に定められています。輸入食品については、厚生労働省や検疫所がサンプリング検査を実施し、基準値超過が確認された場合は流通を禁止、廃棄や返送措置が取られています。
また、農林水産省や環境省も、国内の農産物や水質・土壌・生物に対するモニタリング調査を継続的に実施し、DDTの環境残留状況を監視しています。
さらに、国際的な取り組みとして、2001年に採択された「ストックホルム条約(POPs条約)」により、DDTを含む残留性有機汚染物質(POPs)の製造・使用・貿易が原則禁止され、例外的な公衆衛生目的での使用も厳しく管理されています。日本もこの条約に加盟し、国際協力のもと監視体制を強化しています。
◇今後の課題と注意点
DDTは、今なお一部の国で公衆衛生目的で使われている現実があり、完全なリスク排除は困難です。日本国内での新たなDDT汚染を防ぐためには、引き続き以下のような対策が重要です。
- 輸入食品や農産物の残留農薬検査の徹底
- 違法な持ち込み・流通への厳格な監視と取り締まり
- 環境モニタリングの継続とデータ公開
- 国際協力によるDDTの段階的廃絶支援
また、消費者自身も、輸入食品の産地や農薬使用状況に注意を払い、信頼できる情報に基づいた選択を心がけることが重要です。
日本ではDDTの製造・輸入・使用は厳しく禁止されているものの、世界的には依然として一部の国で使用が続けられています。そのため、食品や環境を通じてDDTが「海外から日本に入り込む」リスクは依然として存在します。今後も、行政・業界・消費者が一体となって監視と対策を徹底し、DDTによる新たな健康・環境リスクを未然に防ぐ努力が求められます。
【あわせて読みたい】
▼【最新版】遠隔地PCB処理相談ガイド|全国法人必見の5ステップ徹底解説
PCB産業廃棄物の運搬や処理を依頼できる会社3選
PCB産業廃棄物の運搬や処理を依頼する際には、安全性や法令遵守が重要です。ここでは、専門性と実績を持つ3社をご紹介します。それぞれが全国対応や独自の技術を活かし、排出事業者の負担軽減や環境保全に貢献しています。
◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送株式会社は、静岡県静岡市に本社を構える産業廃棄物の収集運搬・リサイクル事業の専門企業です。特にPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の適正処理分野で高い専門性を持ち、全国対応の運搬ネットワークと徹底した安全管理体制を強みとしています。
PCB廃棄物の収集運搬作業には、専門講習を修了したスタッフが対応し、JESCO基準の運搬容器やGPS搭載車両を活用して安全かつ確実な輸送を実現。書類作成や届け出のサポート、分析・アドバイスも一貫して提供し、排出事業者の負担軽減に貢献しています。
また、同社は蛍光灯安定器の仕分け作業でも豊富な実績を持ち、全国で約30万本の安定器仕分けを手掛けてきました。現場では安定器を分解し、コンデンサ部分のみ高濃度PCBとして処理、本体は分析のうえ低濃度PCBとして適切に処理することで、コスト削減と環境負荷低減を両立しています。
| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
| 電話番号 | 054-366-1312 |
| 公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
丸両自動車運送は、法令遵守と信頼性の高いサービスで、循環型社会の実現と環境保全に貢献し続けています。
丸両自動車運送株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇株式会社ダイセキ環境ソリューション

ダイセキ環境ソリューション株式会社は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の調査・分析から保管、収集運搬、処分までを一貫してサポートする環境サービス企業です。
主力事業である土壌汚染調査の現場で培ったノウハウを活かし、工場閉鎖や土地売却時のPCB廃棄物対応をはじめ、さまざまな業種の事業者に対し、PCB廃棄物の適正処理を支援しています。変圧器やコンデンサなどの機器がPCB含有物かどうかの判別や、微量PCBの分析も自社計量証明機関で対応。行政への届出や特殊ケースの相談、煩雑な手続きの代行も行います。愛知県弥富市の名古屋トランシップセンターでは、積替え保管や抜油、相積みによる効率的な収運体制を確立。
| 会社名 | 株式会社ダイセキ環境ソリューション |
| 所在地 | 〒467-0852 愛知県名古屋市瑞穂区明前町8-18 |
| 電話番号 | 052-819-5310 |
| 公式ホームページ | https://www.daiseki-eco.co.jp/ |
PCB不含機器の回収や大型機器の解体、不法投棄・漏洩時の土壌調査まで、幅広いサービスでPCB廃棄物の安全・確実な処理に貢献しています。
株式会社ダイセキ環境ソリューションについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼愛知県のPCB産業廃棄物の規定及び優良産廃処理業者認定制度を受けている産廃業者
◇DOWAエコシステム株式会社

DOWAエコシステム株式会社は、長年にわたり有害廃棄物処理分野で培った高度なノウハウと技術を活かし、低濃度PCB廃棄物の総合的な処理サービスを提供しています。
主な対象は変圧器やコンデンサなどの廃電気機器に加え、交換・抜油されたPCB汚染絶縁油、PCB濃度分析時のサンプルキット、作業用ウェスや保護具、コンクリート破片、さらには橋梁など土木構造物の剥離塗膜まで多岐にわたります。全国の拠点で多種多様な廃棄物を効率的に受け入れ・処理できる体制を整えており、移動困難な大型機器については現地での解体や洗浄処理も提案可能です。
| 会社名 | DOWAエコシステム株式会社 |
| 所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 |
| 電話番号 | 0800-222-5374 |
| 公式ホームページ | https://www.dowa-pcb.jp/ |
また、顧客の要望に応じた最適な運搬方法や、現場状況に応じた柔軟な対応も強みです。低濃度PCB廃棄物処理に関する問い合わせや相談には、グループの営業窓口であるエコシステムジャパンが一括して対応し、法令遵守と安全・確実な処理をサポートしています。
DOWAエコシステム株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
まとめ

DDTはかつて「夢の化学物質」として世界中で広く使用されましたが、生態系や人体への悪影響が問題視され、現在は多くの国で製造や使用が禁止・制限されています。特に、1962年にレイチェル・カーソンの著書『沈黙の春』がその危険性を広く知らしめました。
しかし、DDTはマラリアを媒介する蚊を駆除し、多くの命を救った実績もあり、代替品が見つかっていない現状では、発展途上国での感染症対策に限定的に使用されています。
ストックホルム条約に基づき、WHOはマラリアのリスクが高い場合に限り、環境への影響を抑えながらDDTを使用することを推奨しています。このように、DDTは功罪両面を持つ物質として、慎重な管理のもとで今なお重要視されています。
この記事を読んでいる人におすすめ