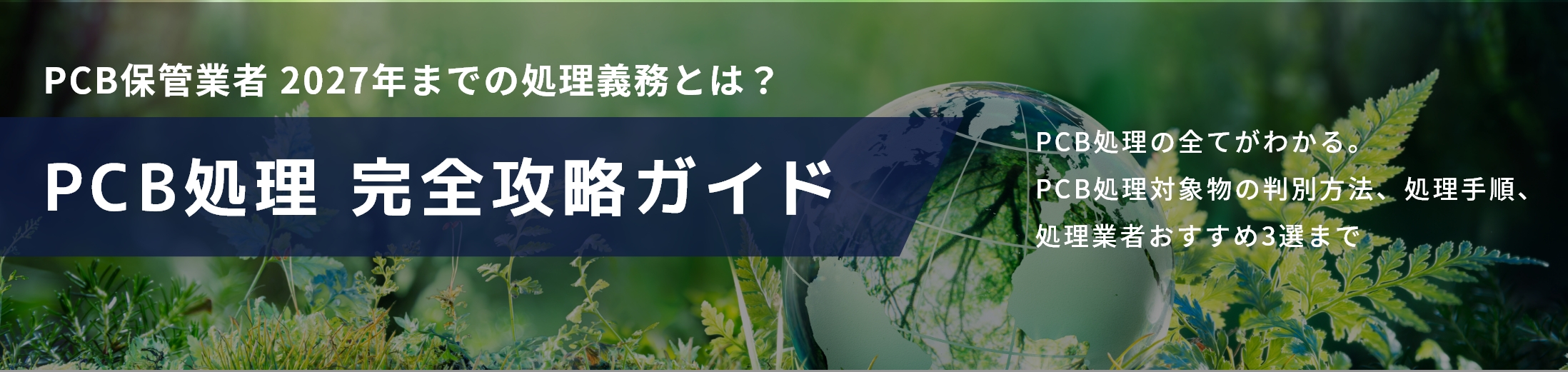経済産業省は、一部の有機顔料に微量のポリ塩化ビフェニル(PCB)が非意図的に副生して含まれるとの報告を受けました。これを受けて、製造・輸入する有機顔料中のPCBの有無と含有量の再確認が求められました。この問題に対応するため、事業者は製造プロセスでのPCB生成を最小限に抑えるための対策を取り入れる必要があります。
目次
有機顔料とは?PCBが含まれる可能性も
PCBは長期的な健康被害を引き起こす可能性があるため、製造・輸入・使用が実質的に禁止されていますが、一部の有機顔料にもPCBが含まれる可能性があることが指摘されました。こちらでは、有機顔料の再調査が必要になった経緯と、有機顔料と無機顔料の違いを解説いたします。
◇再調査が必要となった経緯
経済産業省は、平成24年2月に化成品工業協会から一部の有機顔料に微量のPCBが非意図的に副生して含まれているという報告を受けました。これを受けて、関係事業者に対し、製造・輸入する有機顔料の、PCBの有無および含有量を確認するよう依頼しました。
その結果をまとめ、50ppmを超えるPCB濃度が確認された有機顔料(8品目)については、製造・輸入の中止、使用・出荷の停止、および出荷先からの回収を指導しました。しかし、その後、一部の事業者から、異なる方法で再分析を行ったところ、従来の結果と大きく異なる高い値が得られるケースもあるとの報告がありました。
◇有機顔料とは?無機顔料との違い
有機顔料は、石油由来の化合物から合成される顔料であり、100種類以上の色素があります。これらの顔料は、鮮やかで美しい色合いを実現できますが、太陽光や気候条件の影響を受けやすく、劣化しやすい傾向があります。また、有機顔料は比較的高価です。
一方、無機顔料は、天然の鉱石や金属酸化物から作られる顔料で、合成無機顔料と天然鉱物顔料に分類されます。無機顔料は多くの場合、地味な色調を持っていますが、耐久性や耐候性に優れています。また、無機顔料は比較的安価であり、広く利用されています。
PCBを含む有機顔料の人体への影響
PCBは脂肪に溶けやすいという特性から、体内に徐々に蓄積し、爪の変形、目やに、色素沈着などの症状を引き起こします。このため、PCBを含む有機顔料についても、危険性や人体への影響について、慎重な判断が必要です。
◇リスク評価の方法
有機顔料を含む製品(例:印刷インキ、塗料、合成樹脂、繊維)のリスク評価は、吸入、経皮、経口の暴露経路について考慮されます。まず、製品中の有機顔料の割合が設定されます(例:印刷インキでは12%、塗料では5%)。
次に、顔料中の特定物質の濃度が設定され、最高濃度が適用されます(例:PCB濃度が280ppm)。これらの設定を基に、モンテカルロ法を用いて暴露評価が行われます。この方法は、試行回数10万回を使用し、一般的な暴露シナリオを考慮してリスクを評価します。
◇リスク評価の結果
想定した暴露シナリオに基づき、確認された最高の顔料中PCB濃度を用いて算出した最大暴露量でも、国内外でこれまでに設定されている許容値を上回るケースは確認されませんでした。
この結果を考慮すると、現時点においては、副生PCBを含む有機顔料を含む製品について、製品回収の措置を講じる必要性はないと考えられます。
PCBが副生される過程と副生 PCB の低減策
有機顔料の製造過程で副生されるPCBを減らすために、PCBが副生される過程を明確にして、低減策を実施することが重要です。こちらでは、副生される過程と具体的な低減策をご紹介いたします。
◇PCBが副生される過程
アゾ顔料の製造プロセスでは、まず原料をジアゾ化し、その生成物にカップリング成分を反応させ、さらに熟成して顔料化します。その後、ろ過、水洗、乾燥、粉砕の工程を経て製品が完成します。PCBの副生が生じるのは、主にカップリング反応や熟成の過程で、具体的原因は、反応時に添加される化学物質、未反応の化学物質と考えられます。
◇副生 PCB の低減策
事業者が実施している主な対策は次のとおりです。
まず、顔料を製造している場合の対策です。製造過程で使用する化学物質を変更または調整することで、副生するPCBの生成を抑えます。また、反応の温度や時間などの条件を最適化し、PCBの生成を最小限に抑える工夫も行われています。さらに、製造過程で生じる不純物を取り除くことで、PCBの含有量を減らしています。
次に、クルード(粗顔料)や顔料を輸入している場合の対策です。購入前に顔料の品質を厳密にチェックし、PCB含有量の少ない顔料を選ぶようにしています。また、低PCB含有量の顔料を積極的に選定し、輸入した顔料を洗浄してPCB含有量を低減させてから使用するようにしています。
低減策の実施可能性は、取り扱う製品や事業者によって異なることも明らかになっています。その理由として、製法を変更すると顔料の色の属性や透過性が変化するため技術的な制約があること、事業継続の観点から経済的な制約があることなどが挙げられます。
低減に努める事と適切な管理が重要
PCBの低減を実現させるためには基準値が必要ですが、その基準値を設定するのが困難な状況です。それでも、各事業者は、可能な範囲で低いレベルで管理し低減につとめていくことが求められます。
◇基準値を設ける事が困難
有機顔料中に副生するPCBのリスク評価では、製品による健康リスクや環境汚染を通じた人健康や生態系へのリスクは、50ppmを超える濃度でも低いとされています。しかし、有機顔料中の副生PCBには製造事業者や製品ごとに製法が異なり、低減可能なレベルも異なるため、基準値を設けることが困難です。
製造工程において副生するHCBに関する基準値を示すことは、各製品や事業者の実情を踏まえると難しいと考えられています。
◇可能な範囲で低いレベルで管理
国際的な取組状況やこれまでの暫定的な運用状況から、副生PCB含有濃度が50ppmを超える有機顔料については、製造・輸入および出荷の停止等の措置を今後も継続することが適当と考えられます。
副生PCB含有濃度が50ppm以下の有機顔料についても、製品や事業形態に応じて「利用可能な最良の技術」(BAT)を適用し、工業技術的・経済的に可能な範囲で低いレベルで管理し、さらにその低減に努めることが求められます。
※BATとは、汚染物質の環境への排出を、最大限に抑制するための最新のプロセス、施設、装置のこと
有機顔料は石油由来の化合物から作られ、美しい色合いを持ちますが、太陽光や気候条件に影響されやすく劣化しやすい性質があります。一方、無機顔料は天然の鉱石や金属酸化物から作られ、地味な色調を持ちながらも耐久性や耐候性に優れています。
有機顔料にはPCBという有害物質が含まれる可能性があり、これに対し厳格な管理が求められます。経済産業省では、有機顔料の再調査を行い、一部の製品に高濃度のPCBが含まれていることが判明しました。
このため、製造・輸入・出荷の制限がかけられ、低濃度の管理やPCB削減策が求められています。事業者は、製造工程や原料の選定などでPCBの副生を抑える取り組みを行っていますが、技術的・経済的な制約もあるため、継続的な努力が必要です。