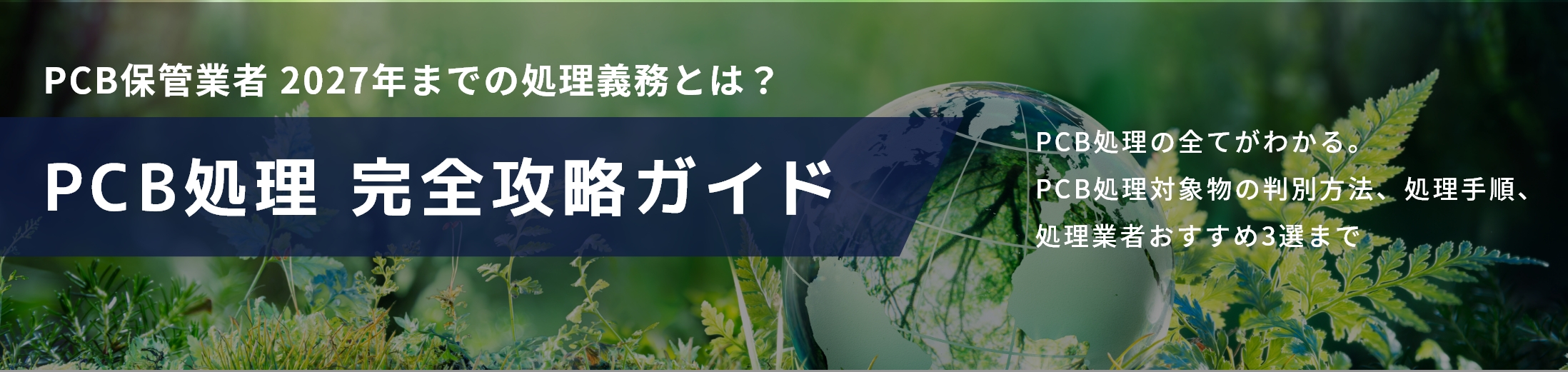産業廃棄物の処理は、複数の段階を経て行われます。まず、分別と保管、収集と運搬、中間処理、再生処理、最終処分の流れがあります。また、特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物を管理するには、PCB廃棄物管理責任者の選任が必要です。この責任者は、正確な排出状況の把握や適切な処分計画の策定を担います。
目次
産業廃棄物の基本~種類・処理について

事業活動によって発生する「産業廃棄物」は21種類に分類されます。産業廃棄物には危険性や毒性を持つ「特別管理産業廃棄物」が含まれるため、取り扱いには注意が必要です。また産業廃棄物は一般廃棄物とは異なり、処理をするには分別と保管、収集と運搬、中間処理、再生処理と最終処分という複数のフェーズを経て処理されます。
◇産業廃棄物とは
産業廃棄物とは廃棄物処理法で定義された廃棄物であり、企業や工場などが事業活動を行うことで発生したものを示します。そして産業廃棄物は焼却残灰や石炭火力発電所から発生する石炭がらなどの「燃えがら」、合成樹脂くずや合成繊維くずなどの「廃プラスチック類」、潤滑油や洗浄用油などの「廃油」など21種類に分類されています。
◇産業廃棄物の種類

産業廃棄物は、その性質や発生源によって以下のように分類されます。
あらゆる業種から排出される物
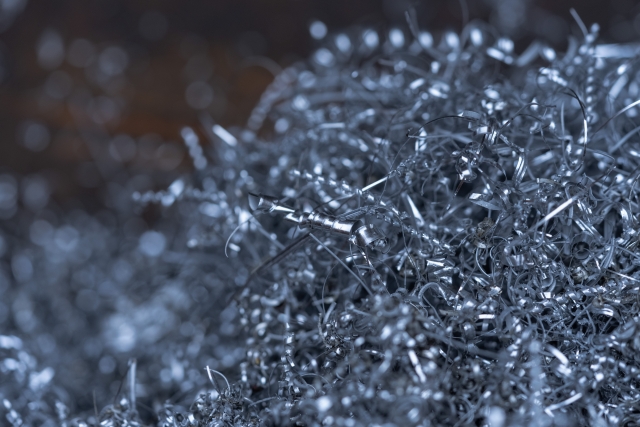
燃えがら:石炭がら、灰カス、焼却残灰など
汚泥:工場廃水処理後の泥状物や製造工程での泥
廃油:潤滑油や切削油、洗浄油など
廃酸:無機酸や有機酸、酸性廃液
廃アルカリ:アルカリ性廃液や洗浄用アルカリ
廃プラスチック類:合成高分子系化合物からなるプラスチック類
ゴムくず:天然ゴムや合成ゴムからなるくず
金属くず:鉄くずや銅線くず、アルミニウムくずなど
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず:ガラス製品やコンクリート、陶磁器から生じる廃棄物
鉱さい:金属の製錬や精錬、溶解から生じる残渣や粉塵
がれき類:工作物の建設や解体に伴う廃材や瓦礫、コンクリート破片など
ばいじん:燃焼施設や集じん施設で集められたダストや粉塵
業種が限定されるもの

紙くず:建設業、パルプ・紙製造業、出版業などで発生する紙くず
木くず:建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業などからの木くず
繊維くず:建設業、繊維工業などからの繊維くず
その他
動植物性残さ:食品製造業や医薬品製造業での動植物性の不要物
動物系固形不要物:食肉処理場や鳥肉処理場からの固形の不要物
動物のふん尿:畜産農業に関連する動物のふん尿
動物の死体:畜産農業に関連する動物の死体
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物:特定の条件下で処理される廃棄物
また、産業廃棄物の中には、爆発の危険性や人体への影響がある毒性によって危険を及ぼすものについて「特別管理産業廃棄物」として指定されているものがあります。身近な特別管理産業廃棄物の例としては、医療現場から発生する感染リスクのある廃棄物があげられるでしょう。
PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物の中でも「特定有害産業廃棄物」に指定され、より厳しい管理や処理が必要となります。
◇産業廃棄物の基本的な処理の流れ

産業廃棄物の基本的な処理は、分別と保管、収集と運搬、中間処理、再生処理と最終処分という流れで進んでいきます。まず産業廃棄物を発生させる排出事業者は、産業廃棄物の種類によって正確に分別をし、適切に保管を行います。
その後、保管された産業廃棄物は収集運搬業者によって収集、運搬され、処理業者へと引き渡されます。そして処理業者が産業廃棄物の種類に合わせて適切な中間処理を行い、再生処理もしくは最終処分を行うことで、産業廃棄物は安全性を保って正しく処理されるのです。
このように産業廃棄物の処理には排出事業者だけでなく、収集運搬業者や処理業者といった複数の業者が関わることになります。そのため各業者が産業廃棄物を適切に取り扱うことが安全な処理に繋がると言えるでしょう。
【あわせて読みたい】
PCB産業廃棄物らしき物が見つかったらどうする?

PCB産業廃棄物は、人の健康や環境に深刻な影響を及ぼすため、適切な判別と処理が不可欠です。しかし、実際に現場で発見された際には「これはPCBかどうか」「どう処分すべきか」と迷うケースも少なくありません。
こちらでは、判別方法から自治体への連絡手順、そして処分期限までを順を追って解説します。
◇1.PCB産業廃棄物に該当するかを確認
PCB廃棄物を安全かつ法令に沿って処分するためには、まず対象となる機器や部材がPCBを含んでいるかどうかを正しく見極めることが欠かせません。変圧器やコンデンサー、安定器など、過去に広く利用されてきた設備の中にはPCBを含有しているものが存在します。
・変圧器・コンデンサー等
ビルや工場の受電設備に使われる変圧器やコンデンサーは、PCBを含有している可能性があります。特に1953年(昭和28年)から1972年(昭和47年)に製造された機器には高濃度PCBが使用されていたケースが多く、調査対象として最も注意が必要です。
判別の基本は銘板の確認で、製造年や型式を基に各メーカーに問い合わせる、または日本電機工業会が公開するリストを参照することが推奨されます。
なお、1991年(平成3年)以降に製造されたコンデンサーや1994年(平成6年)以降に製造された変圧器にはPCBは含まれていないとされていますが、例外的に一部メーカーの旧機種では汚染の可能性が残るため油断はできません。
さらに、古い機器は微量PCBの混入リスクもあり、その場合は絶縁油を分析し濃度を測定する必要があります。自己判断での採油は危険なため、専門業者に依頼することが必須です。感電リスクを避けるため、調査は必ず電気主任技術者や有資格者の立会いのもとで行うことが求められます。
・安定器

1977年(昭和52年)3月以前に建築された事業用建物には、PCBを含有した安定器が残っている可能性があります。対象となるのは工場や事務所ビル、マンション共用部、倉庫など多岐にわたり、過去に事業用として使用されていた建物も調査対象に含まれます。
判別の基本は照明器具や安定器の銘板の確認で、特に1957年(昭和32年)から1972年(昭和47年)に製造された安定器はPCB含有の可能性が高いとされています。銘板情報を基にメーカーへ問い合わせるか、日本照明工業会の情報を参照することが有効です。
使用中の安定器に不用意に触れるのは感電の危険があるため、必ず電気工事業者や専門調査会社に依頼することが推奨されます。横浜市などの自治体では、調査希望者に対して電気工事業界団体を紹介する制度があり、事業者が安心して依頼できる環境も整っています。
放置したままでは環境リスクが高まるため、所有者は早急に調査を実施し、必要に応じてPCB含有安定器を適切に処分することが重要です。
・その他
変圧器や安定器以外にも、1993年(平成5年)以前に製造された電気機器の中にはPCBを含むものがあります。具体的にはX線発生装置、工業用・医療用検査機器、溶接機、昇降機制御盤などが該当します。これらは使用場所が多岐にわたるため、確認漏れが生じやすい点に注意が必要です。
3各業界団体ではPCB使用状況のリストを公開しており、加盟外のメーカー製品については直接照会する必要があります。
さらに、PCB油そのものや、それが付着した汚染物(感圧複写紙、塗膜、廃材など)も濃度に応じて処理区分が異なります。濃度不明のまま処理すると違法や環境リスクにつながるため、必ず分析を経て分類することが求められます。不明点は専門窓口に相談し、誤処理を避けることが安全確保の基本です。
・不明な場合
銘板が不鮮明であったり、メーカーに問い合わせても判断ができないケース、さらに古い機器で製造元が既に存在しない場合には、特別な対応が必要となります。
経済産業省の指針によれば、絶縁油を採取できる機器であれば必ず分析を行うことが推奨されており、分析結果に基づき高濃度・低濃度の区分を行います。小型機器で分析が困難な場合には、高濃度PCBでないことが明らかであれば低濃度PCB廃棄物として処分することも可能です。
また、機器の写真や仕様を添えて産業廃棄物処理事業振興財団に相談することで、外観や形状からPCB含有の有無について助言を受けられる場合もあります。誤った自己判断は法令違反や罰則につながる可能性があるため、必ず行政窓口や専門機関の指導を仰ぎ、法的に適切な対応を取ることが重要です。
◇2.該当した場合は速やかに自治体の窓口へ連絡
PCB廃棄物が確認された場合、まず重要なのは速やかに自治体や所管の環境事務所へ連絡することです。特に高濃度PCB廃棄物は処分期限(令和5年3月末)が既に終了しているため、いま発見されると未処理状態が法令違反にあたる可能性があります。
この場合、PCB特別措置法に基づき、直ちに自治体や地方環境事務所に報告・相談を行わなければなりません。届出を怠ったり、行政指導に従わない場合には、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金といった罰則が科される可能性もあるため注意が必要です。
一方で、低濃度PCB廃棄物については、無害化処理認定施設や都道府県・政令市の許可施設で処分が進められています。松江市の案内によれば、低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日までに処理を完了させる必要があり、保管し続けた場合は改善命令や罰則の対象となります。
処理を確実に行うためには、機器の銘板情報やメーカーへの確認、必要に応じた分析を行ったうえで、早めに処理委託先を決定することが不可欠です。発見時には「まだ期限がある」と油断せず、自治体窓口へ早急に相談し、計画的に廃棄を進めることが求められます。
◇PCB産業廃棄物の処分期限
PCB廃棄物には高濃度と低濃度があり、それぞれ処分期限が法律で定められています。高濃度PCB廃棄物は、変圧器やコンデンサーなどが対象で、2023年(令和5年)3月末までに処分を完了することが求められていました。
期限後に発見した場合は直ちに自治体へ連絡し、指示に従う必要があります。一方、低濃度PCB廃棄物は2027年(令和9年)3月末までが処分期限とされ、無害化処理認定施設や都道府県許可施設での処理が義務付けられています。
期限を過ぎて保管していると改善命令や罰則の対象となるため、早めの確認と処分計画が重要です。
産業廃棄物の処理に関する資格と許可

産業廃棄物の処理には廃棄物処理施設技術管理者の設置や、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可が必要となります。
◇廃棄物処理施設技術管理者
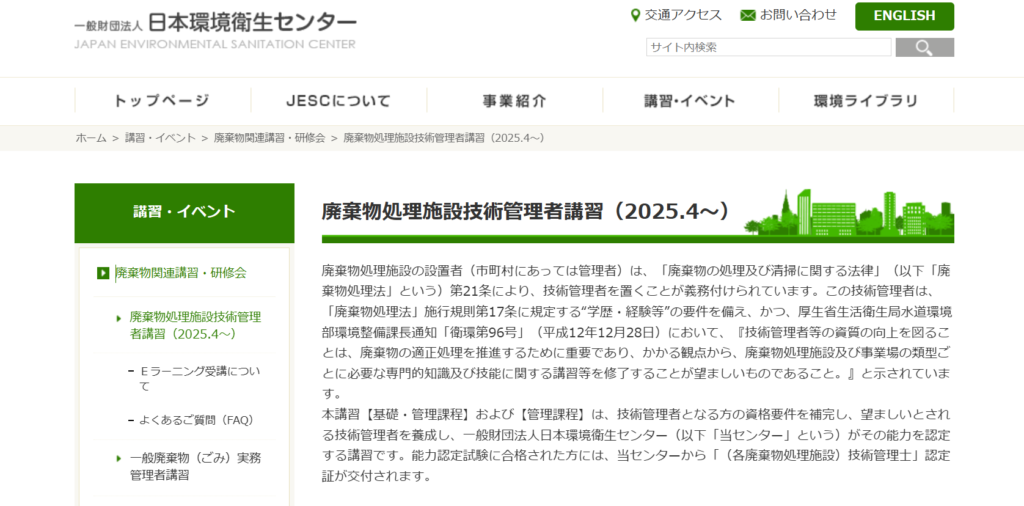
廃棄物処理施設技術管理者は一般廃棄物や産業廃棄物の処理施設で設置する義務のある資格です。廃棄物処理施設技術管理者には、処理施設において運転や点検、維持管理などが関係法令を守りながら適切に実施されているかを監督することが求められます。
そして監督する上では必要に応じて、処理施設設置者に対する改善事項などの意見をしなければなりません。そんな廃棄物処理施設技術管理者の選任要件は、化学部門・上下水道部門・衛生工学部門の技術士や環境衛生指導員、大学の理学・薬学・工学・農学課程で衛生工学または化学工学を修了した者で2年以上の実務経験があるなど、経歴と実務経験が求められます。
またこれらの選任要件を満たしていない場合には、一般財団法人日本環境衛生センターが主催する講習会を修了し、試験に合格することで同等の資格を有していると認められ廃棄物処理施設技術管理者となることが可能となります。
引用元:一般財団法人日本環境衛生センター
◇産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物は排出事業者から委託を受けた産業廃棄物収集運搬業者が回収し、処理施設まで運搬をすることとなります。この時に産業廃棄物収集運搬業者は積み込んだ地域と積み下ろした地域の都道府県や政令都市などからの許可を得た上で、収集運搬の基準に従った回収、運搬を行わなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、施設に係る基準と申請者の能力に係る基準を満たす必要があります。施設にかかる基準では施設の安全性を確認するものであり、産業廃棄物の飛散や悪臭、流出の恐れがなく、収集運搬に使われる車両や容器が業務に適切であるかが求められています。
また申請者の能力に係る基準では、業者自体の信頼性が問われており、運用を行う上での経済的基盤を有するか、産業廃棄物の取扱について十分な知識や技術を有するか、欠格要件に該当しないかなどが求められます。
引用元:環境局
◇産業廃棄物処分業
収集運搬業者から運搬された産業廃棄物は産業廃棄物処分業者によって中間処理された後、リサイクルされるものと分別がなされ、最終的には埋め立てや海面投入によって処分されます。
このような産業廃棄物処分業を行うためには、都道府県・政令都市などから許可を得て、許可番号や有効期限、事業範囲や処理設備について記載された許可証の発行を受けなければなりません。
産業廃棄物処分業の許可を得るには、JWセンターが主催する産業廃棄物処分課程を受講し修了試験に合格する必要があります。また産業廃棄物処分業の許可を得るには欠格要件に該当しないことが条件となります。
引用元:環境省
◇無害化処理認定

無害化処理認定制度とは、PCBやアスベストなど有害性の高い産業廃棄物を安全に処理するために、環境大臣が直接認定を行う仕組みです。
従来は都道府県知事による許可が中心でしたが、平成21年11月の法改正によりこの制度が導入され、処理方法の高度化と信頼性の確保が進められました。認定を受けるためには、実証試験の実施や生活環境影響予測の評価など、厳格な要件を満たすことが求められます。
たとえば、処理施設の技術水準が十分であること、廃棄物を環境基準以下に無害化できること、安定的かつ継続的な運営体制を備えていることなどが条件です。
認定を受けた事業者は、一般廃棄物処理業・産業廃棄物処理業の許可や施設設置許可が不要となり、効率的に処理を進められる一方で、処理結果の報告義務やマニフェストによる厳格な管理を徹底する必要があります。
令和4年3月末時点では全国で34事業者が認定を受けており、低濃度PCB廃棄物の期限内処理を支える重要な制度として機能しています。
【あわせて読みたい】
PCB廃棄物管理をする際に必要な資格

特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物を排出している事業者は廃棄物処理法によって、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任することが義務付けられています。
◇特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
特別管理産業廃棄物管理責任者にはPCB廃棄物の種類や量など、排出状況を正確に把握した上で処分計画を明確化することが求められます。またPCB廃棄物の保管状況を常に把握し、適切な委託業者の選定やマニフェストの交付、保存についても行う必要があります。
◇特別管理産業廃棄物管理責任者になるための条件と取得方法
特別管理産業廃棄物管理責任者には、2年以上の実務経験を有する環境衛生指導員や、大学の理学・薬学・工学・農学課程で衛生工学・化学工学を修了した者で廃棄物処理に係る実務経験を2年以上有する者などが選任されます。
またこれらの選任要件を満たさない場合、JWセンターが主催する講習会を修了し、試験に合格することで特別管理産業廃棄物管理責任者の取得が可能となります。
・処分業者へ引き渡すまで選任が必要
PCB廃棄物を保管する事業者は、処分業者に引き渡すまでの間、適正管理が義務付けられており、必ず「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任する必要があります。
新たにPCB廃棄物を保管する場合には「PCB廃棄物の保管届出書(様式第2号)」を提出し、さらに責任者の設置や変更がある場合には「特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更届出(様式第6号)」の提出も求められます。
責任者は、法令に基づき適切な保管や記録の管理を行い、漏洩や紛失といった事故を防止する役割を担います。届出を怠ると法令違反となるため、廃棄物が処分業者に正式に引き渡されるまで、責任者の選任と届出を確実に行うことが重要です。
PCB廃棄物の処理で求められるその他の資格

PCB廃棄物の適正処理を進めるには、特定化学物質等作業主任者や電気主任技術者のほかにも、専門的な知識や技能を備えた人材が必要です。こちらでは、PCB廃棄物の現場で重要な役割を担うその他の資格について紹介します。
◇特定化学物質等作業主任者
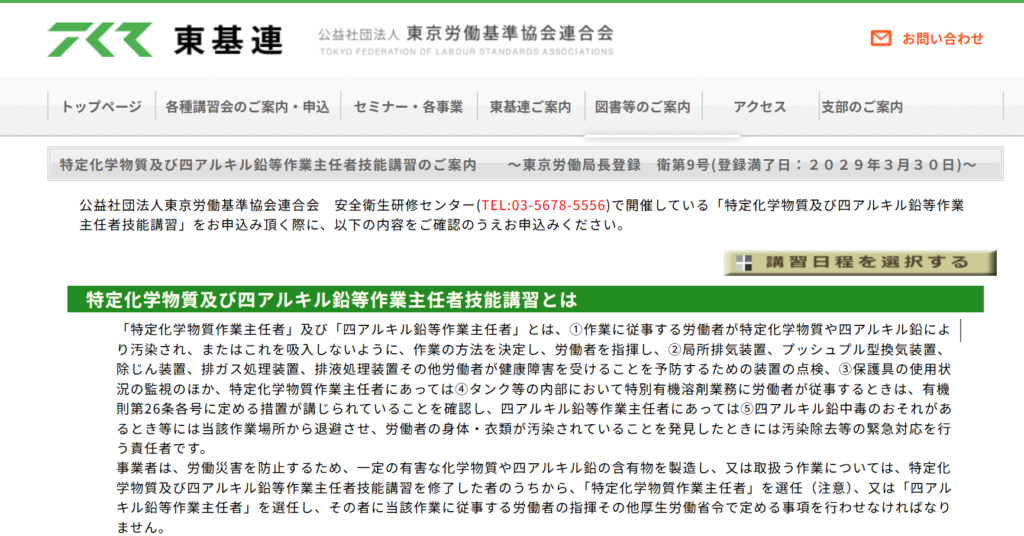
PCB廃棄物の処理作業では、有害物質による労働者のばく露を防止するため、「特定化学物質等作業主任者」の選任が義務付けられています。
作業主任者は労働安全衛生法および特定化学物質障害予防規則に基づく国家資格であり、事業者は必ず技能講習を修了し、修了試験に合格した者を選任しなければなりません。
PCB廃棄物の収集・運搬・解体・処理といった作業は化学的リスクが極めて高く、主任者は現場において作業方法の決定、労働者への指揮監督、局所排気装置や換気装置の点検、保護具の使用状況の確認など、幅広い責任を担います。
講習はおおむね2日間で実施され、健康障害に関する知識、保護具の使用方法、作業環境の改善、関係法令の理解などを学び、最終日に修了試験を受けます。受講資格に制限はなく誰でも受講可能ですが、講義と試験はすべて日本語で行われるため、専門用語を含む内容を理解できる能力が必要です。
合格者には写真付きの修了証が交付され、以後は事業場の安全管理責任者として配置されます。また主任者は単に資格を持つだけでなく、常に知識と技能を更新することが重要とされ、定期的な「能力向上教育」を通じて最新の法令や技術に対応することが推奨されています。
PCB廃棄物処理現場で安全を確保するためには、この主任者の存在が欠かせず、事業者にとって確保すべき不可欠な人材です。
引用元:社団法人東京労働基準協会連合会
◇電気主任技術者

電気主任技術者は、電気事業法で定められた国家資格であり、高圧や特別高圧で受電する工場・ビル、発電所や変電所などに設置される「自家用電気工作物」の保安監督を担う責任者です。
設置者は必ず事業場ごとに選任する義務があり、工事・維持・運用の安全を担保する中核的な存在とされています。
資格は取り扱える電圧に応じて第一種(すべての電気工作物)、第二種(17万V未満)、第三種(5万V未満)の3区分があり、PCBを含む変圧器やコンデンサーの調査・処理においても不可欠です。
試験は一般財団法人電気技術者試験センターが実施しており、一次試験では理論・電力・機械・法規の4科目が出題され、第一種および第二種はさらに二次試験(電力管理・機械制御)が課されます。
受験資格に制限はなく誰でも挑戦可能ですが、合格率は例年10%前後と難関です。合格すると経済産業大臣より免状が交付され、電気設備の安全確保を担う国家資格者として社会的な信頼を得られる点も大きな特徴です。
◇PCB調査士
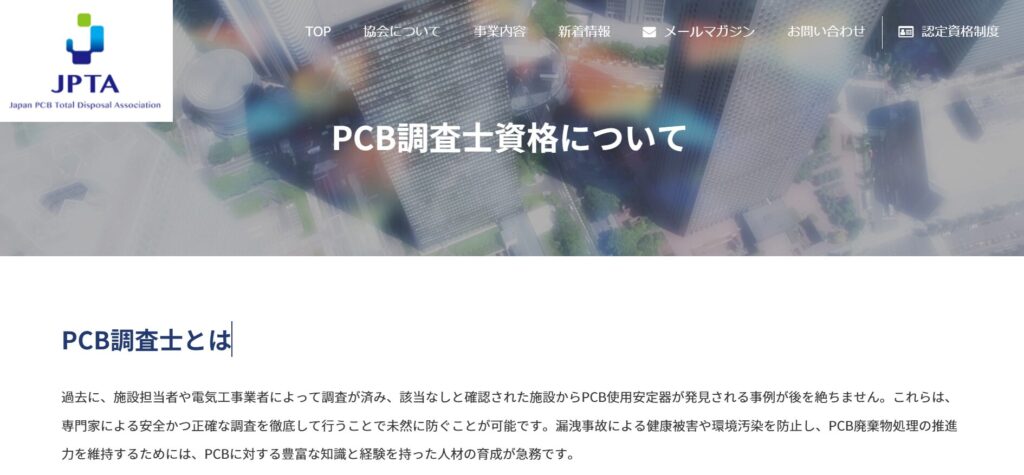
PCB調査士は、PCBを含む可能性のある電気機器や安定器などを正確かつ安全に調査するための専門資格です。
過去には、既に「該当なし」と判断された施設から後にPCB含有安定器が発見される事例も報告されており、専門的知識と経験を持つ人材の必要性から、一般社団法人日本PCB全量廃棄促進協会(JPTA)が認定制度として創設しました。
PCB調査士は、漏洩事故による健康被害や環境汚染を防止し、PCB廃棄物の期限内全廃を実現するための重要な役割を担います。
資格取得には、同協会が実施する1日間の「PCB調査士講習会」を受講し、筆記試験(25問・マークシート方式、80点以上で合格)に合格する必要があります。
対象者は、照明器具の全数調査、廃安定器の分別、PCB濃度分析、低濃度PCB廃棄物の収集運搬や処理に従事する全ての方です。
修了者には認定証が交付され、PCB処理分野で専門性を持つ人材として活動が可能となります。講習は東京会場を中心に年数回実施され、一定人数以上の申込みがあれば地方での開催も行われます。
引用元:日本 PCB全量廃棄促進協会
【あわせて読みたい】
PCB産業廃棄物でおすすめの処理業者3選
PCB廃棄物は厳格な法規制のもとで処理が義務付けられているため、確実に対応できる専門業者を選定することが欠かせません。しかし現場では「どの業者に相談すればよいのか分からない」「期限までに処理を完了できるのか不安」といった声も少なくありません。
そこで、豊富な実績を持ち全国対応の体制を整え、安心して依頼できるおすすめの処理業者3社を紹介します。
◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送株式会社は、静岡県静岡市清水区に本社を置く創業90年以上の老舗企業で、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬や中間処理を手掛けています。
特にPCB廃棄物の処理に強みを持ち、平成17年にPCB廃棄物収集運搬の許可を取得して以来、全国で約3,000件以上の実績を積み重ねてきました。
同社は高濃度・低濃度いずれのPCBにも対応し、収集から運搬、書類作成代行までをワンストップでサポートします。45都府県で許可を取得しており、全国レベルでの対応が可能です。PCB廃棄物作業従事者講習を修了した専門スタッフが作業にあたり、安全性の確保も万全です。
さらに、運搬車両にはJESCO搬入仕様の専用容器・トレイを採用し、運搬中はGPSで位置を管理。万一の事故に備えて最大10億円の保険を完備するなど、安心できる体制を整えています。
| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
| 電話番号 | 054-366-1312 |
| 公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
こうした取り組みにより、丸両自動車運送はPCB廃棄物処理に悩む事業者に「安心・安全・確実」を提供するパートナーであり続けています。PCB処理に迷った際には、まず「丸両におまかせください!」と相談できる存在です。
・蛍光灯安定器の処理事例

丸両自動車運送は静岡県内のある工場からの依頼では、PCB含有の有無を確認しながら分解・分析を実施。その結果、コンデンサ外付けタイプの安定器が見つかりました。このタイプでは外付け部分のコンデンサのみが高濃度PCBとして処理対象となり、本体は低濃度として分類可能です。
同社は安定器を分解し、0.3kgのコンデンサ部分を高濃度PCBとして処理、残り2.5kgの本体を低濃度PCB処理とすることで、全体の処分費用を大幅に削減しました。これにより依頼者はコストを抑えつつ法令に準じた適正処理を実現。
今日までに全国で約30万本以上の安定器仕分けに携わった同社だからこそ可能な対応であり、確かな実績と技術力を示す事例となっています。
丸両自動車運送株式会社の口コミ評判記事はこちら!
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇光和精鉱株式会社

光和精鉱株式会社は、製鉄用ペレット製造と産業廃棄物処理を融合させた独自の事業モデルを持つ企業で、特に「塩化揮発法」による重金属の分離・回収技術に強みを発揮しています。
国内でもトップクラスの塩素系廃棄物処理能力を誇り、排ガスを急冷してダイオキシン再合成を防止するなど、最先端の環境保全設備を備えています。
廃棄物を単に処理するのではなく、焼却残渣をセメント原料や高炉用ペレットに再資源化することで、徹底したリサイクル・資源循環を実現している点が大きな特徴です。
同社は2010年(平成22年)に国内で初めて低濃度PCB汚染廃電気機器の無害化処理認定を取得しました。以来、全国からの依頼に応え、変圧器から小型機器まで幅広く対応しています。ロータリーキルン式焼却炉や固定床炉を用いた処理能力は国内有数で、安全性と確実性を両立させています。
また、北九州市に設置した「infoセンター」では、処理状況や環境モニタリング値を一般公開し、作業風景や搬入車両のGPS運行状況まで確認できる高い透明性を確保しています。
| 会社名 | 光和精鉱株式会社 |
| 所在地 | 〒804-0002 福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46-93 |
| 電話番号 | 0120-582-380 |
| 公式ホームページ | https://www.kowa-seiko.co.jp/ |
さらに、全国に代理店を配置し、提案・現地調査・手続きを含む一貫対応を可能にしている点も大きな強みです。PCB処理期限が迫る中、光和精鉱は「安心」と「安全」を掲げ、低濃度PCB無害化処理のリーディングカンパニーとして高い信頼を集めています。
光和精鉱株式会社の口コミ評判記事はこちら!
◇三友プラントサービス株式会社

三友プラントサービス株式会社は、産業廃棄物処理の分野で70年という実績を誇る老舗企業です。長年にわたり培った経験とデータベースを活かし、処理が困難な特別管理産業廃棄物から一般廃棄物まで、幅広いニーズに対応できる点が強みです。
全国規模の収集運搬ネットワークと複数の中間処理工場を有し、廃棄物の収集・解体・中間処理・最終処分までを一気通貫で対応できる体制を構築しています。さらに、廃棄物削減やリサイクル、エネルギー利用の提案も行い、単なる処理にとどまらない総合的な環境ソリューションを提供しています。
特にPCB処理サービスでは、高濃度・低濃度・微量PCB廃棄物すべてに対応可能です。照明用安定器やトランス、コンデンサ、ウエス、プラスチック、汚泥、金属くずなど多岐にわたる対象物を安全に処理します。
| 会社名 | 三友プラントサービス株式会社 |
| 所在地 | 〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台1-8-21 |
| 電話番号 | 042-773-1431 |
| 公式ホームページ | https://www.g-sanyu.co.jp/ |
解体を組み合わせることでコスト削減を実現し、現地でのリスクを最小限に抑えつつ、迅速かつ確実な処分を可能にしています。さらに全国展開する物流網を活かし、短期間での大量引取りや運搬コスト削減を実現している点も強みです。
三友プラントサービス株式会社の口コミ評判記事はこちら!
まとめ

産業廃棄物は企業や工場などの事業活動によって発生し、その性質や発生源に応じて21種類に分類されます。特に、危険性や毒性を持つ特別管理産業廃棄物は、処理や取り扱いに高度な注意が必要です。これらの廃棄物は、一般廃棄物と異なり、処理には分別と保管、収集と運搬、中間処理、再生処理、最終処分といった複数の段階が必要です。
産業廃棄物の適切な処理には、廃棄物処理施設技術管理者の設置や産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可が不可欠です。特に、PCB廃棄物を管理する際には、PCB廃棄物管理責任者の選任が法律で義務付けられています。
この責任者は、PCB廃棄物の排出状況を正確に把握し、適切な処分計画を立案する役割を担います。 資格取得には、一般的に実務経験や特定の講習修了などの要件があります。産業廃棄物の処理には、排出事業者や収集運搬業者、処理業者など、複数の関係者が関わるため、各段階での適切な取り扱いが安全な処理につながります。
この記事を読んでいる人におすすめ
この記事を読んでいる人におすすめ
この記事を読んでいる人におすすめ