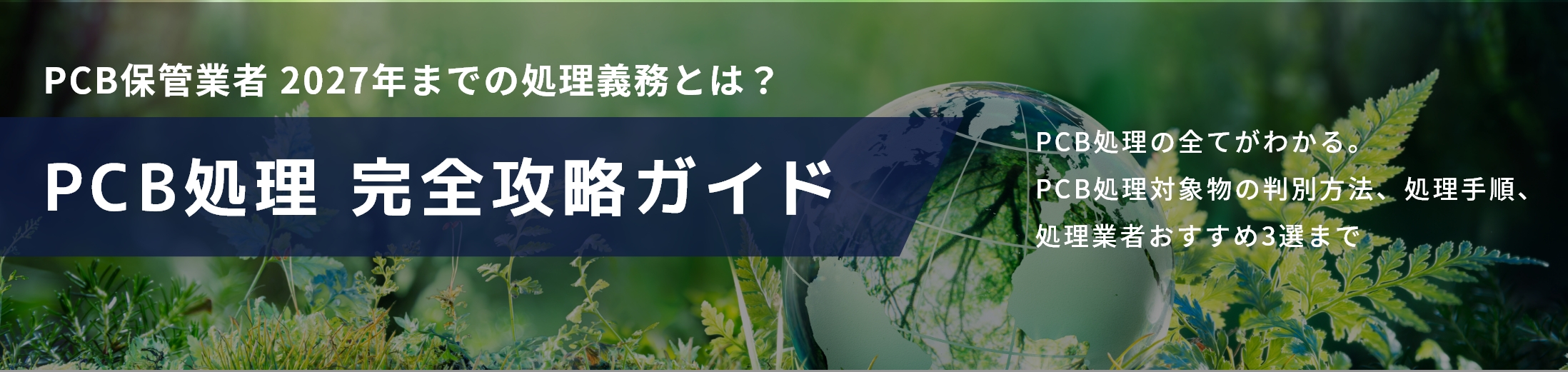特別管理産業廃棄物は、特定の危険性を持つ産業廃棄物です。特別管理産業廃棄物の処理には特別な資格が必要となります。また処理する際には、各都道府県で許可をとらなければなりません。
今回は特別管理産業廃棄物を扱う際の注意点や専門資格について解説します。
目次
特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物よりも危険性が高く、爆発性・毒性・感染性などの特性を持つ廃棄物を指します。廃棄物処理法施行令第1条および第2条の4により定義され、人の健康や生活環境への深刻な被害を防ぐため、厳格な規制と管理が必要とされています。
◇主な特別管理産業廃棄物の種類
以下の廃棄物が特別管理産業廃棄物に分類されます。
- 危険な廃液類:
- 引火点70度未満の揮発油類、灯油類、軽油類
- pH2.0以下の強酸性廃液(廃酸)
- pH12.5以上の強アルカリ性廃液(廃アルカリ)
- 感染性廃棄物:
- 血液が付着した注射針
- 感染症病原体が付着する可能性のある廃棄物
- 特定有害物質:
- PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む廃油、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず
- アスベストを含む建材や廃石綿
- 重金属やダイオキシン類を含む燃え殻、ばいじん、汚泥
◇処理と管理の原則

特別管理産業廃棄物の処理では「排出者責任の原則」が適用されます。事業者は以下を遵守しなければなりません。
- 適正な処理:
- 法令に基づき自ら処理するか、許可を得た専門業者に委託
- 管理体制:
- 管理責任者の設置
- マニフェスト(管理票)による追跡管理
- 違反時の罰則:
- 不適切な処理や不法投棄には厳しい罰則が科される可能性
◇専門業者への依頼の必要性

自治体による無料回収の対象外であるため、PCBやアスベストなどの廃棄物は専門業者への依頼が必須です。専門知識や設備がないと適切な処理は困難であり、環境保全や法令遵守のためにも専門業者との連携が重要です。
特別管理産業廃棄物は厳しい基準の下で管理されており、事業者には法令を遵守した適正な処理が求められます。これにより、環境保全と人々の健康が守られます。事業者はその性質や処理方法を正確に理解し、適切な管理体制を確立することで、社会的責任を果たすことが求められます。
【あわせて読みたい】
特別管理産業廃棄物を扱う際の注意点

特別管理産業廃棄物を安全かつ適切に処理するためには、法令を遵守し、管理体制を徹底することが欠かせません。特にその危険性や特殊性から、通常の産業廃棄物以上に厳格な規制が設けられています。
以下では、取り扱い時に注意すべき5つのポイントについて、具体的な法令や実務的な観点を踏まえながら詳細に解説します。
◇特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務

特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、事業所ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任する義務があります。これは、廃棄物処理法第12条の2第8項に明記されており、責任者を設置しなかった場合には30万円以下の罰金が科される場合もあります。
この制度は、廃棄物の適正処理を徹底し、不適切な管理による環境汚染や健康被害を防止する目的で導入されています。
管理責任者の主な役割は、廃棄物の収集、運搬、保管、処理・処分に関わる安全管理と、法令に基づいた適正な管理の実施です。例えば、感染性廃棄物を取り扱う場合は、適切な防護措置を講じ、廃棄物が外部に漏出するリスクを最小限に抑える必要があります。
さらに、責任者は自治体が定める報告義務を果たす必要があり、選任・変更・廃止の際には自治体への届出が必要な場合もあります。
資格要件についても厳格に定められており、環境省令で規定された資格や実務経験が必要です。感染性廃棄物の場合は医師や薬剤師など医療資格者、その他の場合は理学・工学分野の知識や経験を持つ者が適任とされます。
近年では、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を受講し、修了試験に合格することで資格を取得する方法も広がっており、多様な選択肢が提供されています。
◇自ら処理する場合の帳簿義務

特別管理産業廃棄物は、原則として許可を受けた専門業者に運搬や処分を委託することが推奨されていますが、事業者自らが処理することも可能です。ただし、自ら処理する場合には、廃棄物の種類、数量、処理方法、処理日などを帳簿に詳細に記録し、5年間保存する義務があります。
帳簿管理は、行政指導や万が一の事故が発生した際に重要な証拠となります。また、適正処理を行ったことを第三者に示す手段としても重要です。
例えば、PCB廃棄物やアスベスト廃棄物など、特に高い危険性を持つ廃棄物を扱う場合は、帳簿に加えて関連する処理記録を詳細に保存しておくことが推奨されます。これにより、事業者の適正処理能力を証明し、社会的信頼を向上させることが可能です。
◇普通産業廃棄物との混合防止

特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性などの強い危険性を持つため、普通産業廃棄物や一般廃棄物と混合して保管や運搬を行うことは禁止されています。この混合を防ぐためには、専用の保管場所を設け、他の廃棄物と明確に区別して管理することが必要です。
具体的には、特別管理産業廃棄物専用のコンテナや保管設備を用意し、廃棄物の種類や性質を明確に示すラベルを貼付することが求められます。
また、保管場所には適切な防護措置を講じ、漏洩や流出のリスクを徹底的に防止する必要があります。混合が発覚した場合、すべての廃棄物が特別管理産業廃棄物として扱われ、処理コストが大幅に増大するだけでなく、法的な責任を問われる可能性もあります。
◇電子マニフェストの運用義務
特別管理産業廃棄物においては、マニフェスト制度が適用されており、排出事業者は廃棄物の処理状況を把握し、不法投棄や不適正処理を防ぐ責任があります。年間50トン以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業所では、電子マニフェストの使用が義務化されており、紙の管理票と比較して即時性や追跡性に優れています。
電子マニフェストの運用により、排出事業者は処理状況をリアルタイムで確認でき、業務効率化やコンプライアンス強化が期待されます。導入の際は、電子マニフェストを提供するシステムベンダーと契約し、社内の関係者へ使用方法を周知徹底することが必要です。
◇マニフェスト返却遅延時の行政報告義務

マニフェストは、廃棄物の処理が完了したことを証明する重要な管理票であり、特別管理産業廃棄物の場合、中間処理または最終処分が完了してから60日以内に返却される必要があります。この返却が遅延した場合、事業者は状況を確認し、所管自治体に報告する義務があります。
報告の際は、遅延理由や現状、今後の対応策を具体的に記載し、行政機関の指示に従って適切な対応を行わなければなりません。未報告や対応の遅れは行政指導や罰則の対象となるため、事前にリスクを予防する管理体制を整備することが重要です。
特別管理産業廃棄物の取り扱いは、その危険性や特殊性から、通常の産業廃棄物よりもはるかに厳格な規制と管理体制が敷かれています。事業者は、廃棄物の性質や分類を正確に理解し、適正な管理を行うことが求められます。
また、最新の法改正や自治体の条例を常に把握し、専門業者やコンサルタントと連携して適正な管理体制を維持することが重要です。
特別管理産業廃棄物の適正処理は、環境保全と社会的責任を果たすための重要な要素です。企業の信頼性を高め、持続可能な社会の実現に寄与するためにも、高い意識を持ち、継続的な改善に努めることが求められます。
【あわせて読みたい】
▼PCB塗膜が発見されたときの対応事例と廃棄物削減への取り組み
特別管理産業廃棄物を扱うためには専門の資格が必須

特別管理産業廃棄物の取り扱いには危険が伴うため、排出事業者が扱う場合には専門の資格が必須です。当然のことながら、特別管理産業廃棄物の処理も、資格とノウハウを持った処理業者に依頼しなくてはいけません。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割

特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物処理法に基づき、爆発性・毒性・感染性などの危険性を持つ特別管理産業廃棄物の管理全般を担う重要な役割を果たします。事業場ごとに選任が義務付けられ、その業務内容は主に「排出状況の把握」「処理方法の確保」「処理計画の立案」の3つに分類されます。
◇排出状況の把握

「排出状況の把握」は、事業所から排出される特別管理産業廃棄物の種類や量を正確に確認し、不法投棄や処理漏れを防ぐための基礎となる業務です。この業務には、日常的な記録の作成や現場巡回が含まれ、発生源ごとの管理台帳を整備することが求められます。
また、廃棄物ごとに適切な分類を行い、安全かつ効率的に管理する仕組みを構築することも重要です。
◇処理方法の確保

次に挙げられる「処理方法の確保」では、責任者が廃棄物の保管状況を常に監視し、法令に定められた基準を遵守しているかを確認します。廃棄物の処理や運搬を委託する場合には、信頼性の高い許可業者を選定し、委託契約を適切に締結します。
その際、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付を徹底し、処理が最終段階まで適正に行われたことを証明する仕組みを確立します。
マニフェストは紙で保管する場合、5年間の保管義務がありますが、電子マニフェストを利用すれば、保管・管理の効率化が可能です。電子化により情報の即時共有が可能となり、業務負担の軽減も期待されます。
◇処理計画の立案

三つ目の「処理計画の立案」では、責任者が廃棄物処理の方法や日程に関する計画を策定し、事業所全体の廃棄物管理を指揮します。計画には、廃棄物発生の抑制や再資源化の推進、さらには緊急時の対応策も含まれます。この業務を通じて、事業所の環境管理体制を強化し、長期的な持続可能性を確保する役割を担います。
さらに、委託先業者の処理状況を定期的に確認し、必要に応じて現地視察や書類確認を行うことも責任者の重要な業務です。このような監視活動を通じて、不適正処理や不法投棄のリスクを低減することが可能です。
◇法令遵守と柔軟な対応
特別管理産業廃棄物管理責任者には、法改正や自治体の指導に対応して管理体制や手順を適宜見直す柔軟性が求められます。適切な知識と実務経験を持つことに加え、廃棄物管理に関する最新情報を常に把握することが、信頼性の高い管理体制の維持につながります。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、排出から最終処分までの全工程を一元的に管理するキーパーソンです。その活動を通じて、法令遵守と環境保全の両立を図り、事業所の安全・安心な廃棄物管理を支えます。この役割は、企業が社会的責任を果たすうえで不可欠な存在といえるでしょう。
特別管理産業廃棄物責任者の選任要件と取得方法

特別管理産業廃棄物管理責任者の選任要件や取得方法は、排出する廃棄物の種類によって大きく異なります。特に「感染性産業廃棄物」を排出する事業者と、それ以外の事業者では、求められる資格や経験などが細かく定められています。
◇感染性産業廃棄物を排出する事業者の選任要件
感染性産業廃棄物とは、医療機関や研究機関などから排出される、感染症の原因となりうる血液や体液、注射針などを含む廃棄物です。この場合、特別管理産業廃棄物管理責任者として選任できるのは、以下のいずれかの資格や経験を有する者に限られます。
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士
・環境衛生指導員として2年以上の実務経験を有する者
・大学や高等専門学校で医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学などの課程を修了した者、またはそれと同等以上の知識を有すると認められる者
これらの資格や学歴が必要となるのは、感染性廃棄物が人の健康や公衆衛生に与えるリスクが高いためです。なお、医療関係機関向けの特別管理産業廃棄物管理責任者講習会もあり、受講資格に特別な学歴や実務経験は求められませんが、修了することで管理責任者の資格を得ることができます。
◇感染性産業廃棄物を排出しない事業者の選任要件

一方、感染性産業廃棄物を排出しない事業者の場合、選任要件はやや幅広く設定されています。主な要件は以下の通りです。
・環境衛生指導員で2年以上の実務経験がある者
・大学や高専で理学、薬学、工学、農学などの課程を修了し、衛生工学や化学工学などの関連分野で2年以上の実務経験がある者
・短大や高専卒業で理学、薬学、工学、農学などの課程を修了し、4年以上の実務経験がある者
・高校や旧制中学で土木科や化学科を修了し、6年以上の実務経験がある者
・学歴要件がない場合でも、10年以上の実務経験があれば選任可能
また、これらの要件を満たしていない場合でも、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を受講し、修了することで資格を取得できます。講習会は1日間で約5.5時間、受講料は13,200円(2025年度)です。修了証を取得すれば、学歴や実務経験に関係なく管理責任者に選任できます。
◇特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可要件と申請方法
特別管理産業廃棄物を収集・運搬するには、都道府県や政令市ごとに許可を取得する必要があります。運搬する廃棄物が複数の自治体をまたぐ場合、それぞれの自治体で許可申請が必要です。
許可申請の流れは以下の通りです。
・講習会(特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程)の受講(3日間)
・事業概要のヒアリングや必要書類の準備
・申請書や事業計画書、運搬車両・容器の写真、資金計画、法人登記事項証明書、納税証明書などの提出
・審査後、許可証の交付
申請費用は、オンライン講習受講料が37,400円、対面講習は46,200円(2023年8月現在)、新規許可申請料は81,000円です。なお、PCBなど特定の廃棄物を扱う場合は、追加で専用の講習会の修了が必要になる場合があります。
また、許可を取得するためには、施設や車両が基準を満たしていること、申請者が欠格要件に該当しないこと(例:過去に重大な法令違反がないこと)なども条件となります。
特別管理産業廃棄物管理責任者の選任や収集運搬業の許可取得には、専門的な知識や経験が求められ、法令や自治体ごとの細かな規定に従う必要があります。講習会の受講や資格取得を通じて、適正な廃棄物管理を行うことが、企業の社会的責任と環境保全の両立に不可欠です。
PCB廃棄物の適正処理と法的義務

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物は、人体や環境に有害な物質を含むため、厳格な法規制のもとで処理が義務付けられています。現在、PCB廃棄物は「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類されており、それぞれ処理期限が異なります。
高濃度PCB廃棄物の処理期限はすでに終了しており、令和4年(2022年)3月31日(変圧器・コンデンサ等)、令和5年(2023年)3月31日(安定器・汚染物質等)までに処理が完了しています。
一方、現在残されているのは低濃度PCB廃棄物であり、その処理期限は令和9年(2027年)3月31日までと定められています。この期限はPCB特別措置法によって厳格に定められており、延長の予定はありません。
低濃度PCB廃棄物には、古い変圧器やコンデンサなどが含まれており、所有している機器が該当するかどうか分からない場合は、専門機関での調査が必要です。
処理期限が迫ると、全国の処理施設が混雑し、予約が取れず計画通りに処分できないケースが増えることが予想されます。
そのため、所有者は早めに処理計画を立て、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)への「予備登録」や「搬入荷姿登録」など、必要な手続きを進めておくことが重要です。JESCOへの登録や契約、搬入には一定の時間がかかるため、余裕を持った対応が求められます。
期限内に処理を終えなかった場合、環境大臣や都道府県知事から改善命令が出されることがあります。さらに、改善命令に従わなかった場合や届け出義務を怠った場合には、PCB特別措置法に基づき「3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方」という厳しい罰則が科される可能性があります。
PCB廃棄物の所有者は、法令に基づく届出や保管、適切な処理を確実に行う必要があります。特に低濃度PCB廃棄物については、処理期限まで残りわずかとなっているため、施設内の機器を再点検し、該当する廃棄物がないか確認することが推奨されます。
処理の手続きや登録方法については、JESCOや自治体の窓口、専門の処理業者に早めに相談し、計画的な対応を進めてください。
このように、PCB廃棄物の適正処理は、事業者の法的義務であると同時に、社会的責任でもあります。期限を過ぎてしまうと大きなリスクが伴うため、早期の対応が不可欠です。
【あわせて読みたい】
▼PCB産業廃棄物を発見したら?保管はどうする?よくある質問をまとめたQ&A集
PCB廃棄物の処理を検討するならおすすめ処理業者3選
PCB廃棄物処理に注力する企業3社は、収集運搬から分析、処分までの一貫対応を提供し、環境保全と法令遵守を支援しています。
◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送株式会社は、産業廃棄物のリサイクルと適正処理を通じ、循環型社会の実現を目指しています。特にPCB廃棄物の処理に注力し、専門講習を受けたスタッフが収集運搬から分析、書類作成まで一貫対応します。
静岡県内の工場から依頼を受けた際には、蛍光灯安定器のPCB含有有無の確認と、分解・分析作業も実施しています。コンデンサ部分のみを高濃度PCBとして処理し、本体は低濃度PCBとして適切に処理することで、処分費用の大幅な削減を実現しています。
| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
| 電話番号 | 054-366-1312 |
| 公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
また、SDGsの実践を通じ、エネルギー効率化や気候変動対策などに取り組みます。持続可能な経営を掲げ、信頼と実績をもとに社会的責任を果たすパートナー企業です。
丸両自動車運送株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇三友プラントサービス株式会社

三友プラントサービス株式会社は、産業廃棄物処理と環境保全を専門とする企業グループです。廃棄物の収集・運搬から適正処理までワンストップで対応し、長年の経験と技術力を活かしたサービスを提供しています。
同社は土壌汚染リスクの低減や省エネルギー化の支援にも注力。環境保全装置やサービスの開発を通じ、持続可能な社会づくりに貢献しています。また、PCB廃棄物の安全かつ迅速な処理にも対応可能です。
| 会社名 | 三友プラントサービス株式会社 |
| 所在地 | 〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台1-8-21 |
| 電話番号 | 042-773-1431 |
| 公式ホームページ | https://www.g-sanyu.co.jp/ |
高濃度PCBは指定機関、低濃度PCBは認定施設で無害化処理を実施。効率的な施設運用でコスト削減と迅速対応を実現し、企業の環境リスク低減と法令遵守を一貫してサポートします。
三友プラントサービス株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
◇株式会社ダイセキ環境ソリューション

株式会社ダイセキ環境ソリューションは、PCB廃棄物の調査・収集運搬・処分を一貫して手掛ける環境ソリューション企業です。PCBは毒性が判明し製造・使用が禁止され、2027年3月までの適正処分が法令で義務付けられています。同社はこの分野で豊富な実績を持ち、行政手続き代行や調査・分析、収集運搬の効率化を支援しています。
名古屋トランシップセンターを拠点に、低濃度PCB廃棄物の収集運搬・保管を効率的に実施し、コスト削減を実現。屋上や地下の機器引き出し作業、大型機器の解体、PCB非含有機器の回収も手掛け、包括的な廃棄物処理を行っています。
| 会社名 | 株式会社ダイセキ環境ソリューション |
| 所在地 | 〒467-0852 愛知県名古屋市瑞穂区明前町8-18 |
| 電話番号 | 052-819-5310 |
| 公式ホームページ | https://www.daiseki-eco.co.jp/ |
さらに、不法投棄や漏洩対策にも注力し、企業や行政の多様なニーズに対応。環境保全と法令遵守を両立し、廃棄物処理における信頼されるパートナーとして幅広く貢献しています。
株式会社ダイセキ環境ソリューションについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼愛知県のPCB産業廃棄物の規定及び優良産廃処理業者認定制度を受けている産廃業者
まとめ

特別管理産業廃棄物は、特定の危険性を持つ産業廃棄物です。特別管理産業廃棄物には厳格な処理要件が課せられ、専門業者によって取り扱わなければなりません。
主な特別管理産業廃棄物には廃油、廃アルカリ、PCB汚染物、廃石綿(アスベスト)、廃酸、感染性産業廃棄物などが含まれます。
特別管理産業廃棄物の処理には特別な資格が必要で、特別管理産業廃棄物責任者や産業廃棄物収集運搬業者がこれらの廃棄物を適切に処理する役割を果たします。また各都道府県で許可をとる必要があり、規制に従うことが求められます。
この記事を読んでいる人におすすめ