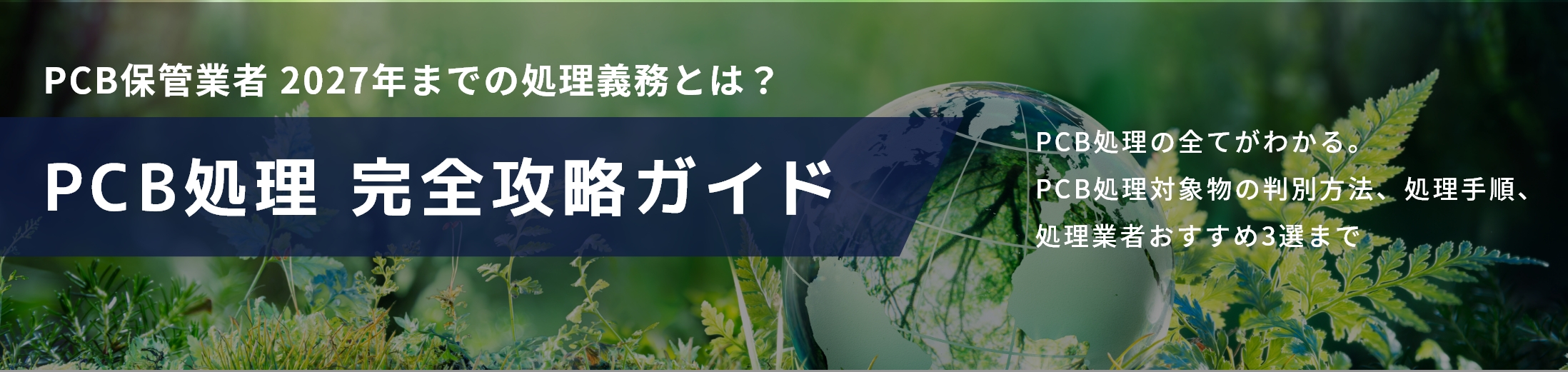産業廃棄物の処理には、法律で定められた厳格なルールがあり、違反した場合には重い罰則が科せられます。許可を持たない業者への委託や無許可営業、不法投棄や焼却などの違反行為が発覚すると、企業の信頼を大きく損ない、深刻な影響を受けることになります。
こちらでは、産業廃棄物処理における主な罰則と、実際に起こった違反事例を紹介し、企業がどのような点に注意すべきか、違反を未然に防ぐための教訓を解説します。
目次
廃棄物処理法についておさらい

廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、日本における廃棄物の適正な処理と環境保全、公衆衛生の向上を目的として1970年(昭和45年)に制定された基本法です。
この法律は、戦後の高度経済成長に伴い急増したごみや産業廃棄物による環境汚染・公害問題への対応として生まれ、廃棄物の発生抑制から最終処分までの一連の流れを厳格に規制しています。
◇廃棄物処理法の目的と基本構造

廃棄物処理法の最大の目的は、廃棄物の排出を抑制し、適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分などを通じて生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることです。法律第1条には、「廃棄物の排出を抑え、廃棄物の適正な処理を行い、生活環境を清潔に保つことで、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図る」と明記されています。
廃棄物処理法では廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別しています。一般廃棄物は主に家庭などから排出されるごみ、産業廃棄物は事業活動に伴って発生する特定の廃棄物(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など20種類)を指します。また、輸入廃棄物も産業廃棄物に含まれます。
◇排出者責任と汚染者負担の原則

廃棄物処理法の根底には「排出者責任」と「汚染者負担の原則(PPP:Polluter-Pays Principle)」があります。これは、廃棄物を排出した者が自らの責任と費用で適切に処理することを求めるもので、特に産業廃棄物については排出事業者自身が処理責任を負うことが明確に規定されています。一般廃棄物については市町村が処理責任を持ちます。
◇法律制定の背景
廃棄物処理法が制定された背景には、戦後の急激な経済成長と都市化に伴う廃棄物の爆発的増加があります。高度経済成長期には大量生産・大量消費のライフスタイルが定着し、ごみの量が急増。不法投棄や不適切な処理による環境汚染、公害が社会問題化しました。
従来の「清掃法」(1954年制定)では対応が困難となり、1970年の「公害国会」で廃棄物処理法が制定されました。
この法律によって、廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・施設・業者の基準などが明確化され、廃棄物の発生から最終処分までの一連の流れが厳格に規制されるようになりました。また、リサイクルや減量化の推進も重要な柱として位置づけられています。
◇違反事例と罰則

廃棄物処理法は、廃棄物の適正な処理を確保するため、違法な投棄や不適切な処理に対して厳しい罰則を設けています。たとえば、無許可での処理や不法投棄が発覚した場合には、個人・法人を問わず懲役刑や罰金刑が科されることがあります。
また、排出事業者が処理委託先を適切に管理せず、委託先が違法行為を行った場合も排出者責任が問われます。
◇法改正と現代的課題
廃棄物処理法は制定以来、社会状況や技術の進歩に合わせてたびたび改正されてきました。近年の主な改正点には、事業所外での産業廃棄物保管の事前届出制、処理施設の定期検査義務、優良処理業者の優遇措置、産業廃棄物減量計画の作成義務などがあります。
また、リサイクルや循環型社会の実現を目指した関連法の整備も進められています。
廃棄物処理法は、日本の環境保全と公衆衛生の根幹を支える法律です。排出者責任や汚染者負担の原則のもと、廃棄物の発生抑制から最終処分までの適正な管理を規定し、不法投棄や環境汚染の防止、リサイクルの推進を図っています。
違反には厳しい罰則が科されるため、事業者・自治体・市民のすべてが法令遵守の意識を持つことが重要です。
【あわせて読みたい】
▼PCB産業廃棄物の調査から搬入まで!一括対応が強みの株式会社ティーエムハンズ
廃棄物処理法で定められた主な罰則

画像出典:photoAC
廃棄物処理法には、適正な廃棄物処理を行わない場合に科される罰則が定められています。これには、許可を持たない業者への委託や無許可営業、不法投棄やマニフェストの不交付などが含まれます。
こうした違反行為が発覚した場合、罰則は非常に厳しいものとなっており、企業や個人に大きな責任が問われることとなります。廃棄物処理法で定められた主な罰則について詳しく解説します。
◇許可を持たない業者に委託した場合のリスクと罰則

排出事業者が許可を持たない業者に廃棄物の処理を委託した場合、廃棄物処理法第25条第1項第6号に基づき、「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方」という非常に重い罰則が科されます。
さらに、委託基準違反として廃棄物処理法第26条が適用される場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科されることもあります。
このような違反が発覚した場合、排出事業者は刑事罰だけでなく、行政処分(営業停止命令や業務改善命令など)や、場合によっては民事訴訟(損害賠償請求)にも発展するリスクがあります。
実際に、PCB廃棄物を無許可業者に委託した地方自治体職員が罰金刑を受けた事例も報告されており、地方公共団体や企業にとっても重大なコンプライアンス問題です。
◇委託先業者の責任と排出事業者の最終責任

廃棄物処理法では、委託先業者が適切な許可を持ち、かつ委託契約書を法令に基づいて締結していることが求められます。たとえ委託先業者が不適切な処理や不法投棄を行った場合でも、排出事業者には「排出者責任」が課せられており、最終的な責任を免れることはできません。
つまり、許可業者であっても、処理可能な範囲や事業内容を逸脱している場合や、適切な処理ができない業者に委託した場合も違反となります。
◇無許可営業の罰則と社会的影響
一方、廃棄物の収集運搬や処理を無許可で行った業者(無許可営業)にも、廃棄物処理法第25条第1項第1号により、「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方」が科されます。
無許可営業は不適切な処理や不法投棄につながりやすく、環境汚染や地域住民への健康被害の原因となるため、行政当局による厳しい監視と摘発の対象となっています。
違法営業が発覚した場合、業者には事業停止命令や罰金が科されるだけでなく、企業や自治体の信頼失墜、社会的批判、さらには取引先からの契約解除や取引停止といった経済的損失にもつながります。
◇実務上の注意点とコンプライアンス強化の必要性

排出事業者は、廃棄物処理を委託する際、必ず許可証の有無や許可範囲(処理できる廃棄物の種類や地域など)、契約書の内容を事前に確認し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を適切に運用することが求められます。
また、委託先の処理状況や最終処分先の確認も重要であり、定期的な監査や現地確認を行うことで、不適正処理や違法行為の未然防止につながります。
廃棄物処理法における無許可業者への委託や無許可営業は、厳罰の対象となるだけでなく、排出事業者や業者双方にとって大きなリスクを伴います。法令遵守とコンプライアンスの徹底、信頼できる許可業者の選定、適切な契約・管理体制の構築が、環境保全と企業・自治体の社会的信頼を守るために不可欠です。
◇不法投棄・不法焼却

不法投棄や不法焼却は、環境への直接的な悪影響を引き起こす行為であり、廃棄物処理法の中でも特に重い罰則が定められています。不法投棄が行われた場合、廃棄物の排出者だけでなく、関与した業者や土地所有者にも責任が及ぶことがあります。
また、不法焼却は大気汚染を引き起こし、周囲の住民や生態系に悪影響を及ぼすため、厳しく取り締まられています。発覚した場合、罰金だけでなく、刑事罰が科されることもあります。
◇マニフェストの不交付や必要事項の記入漏れ
廃棄物処理法では、廃棄物の処理過程を適正に管理するために、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務付けられています。マニフェストには、廃棄物の排出元、運搬業者、処理業者、最終処分先などの情報が記載されており、この情報をもとに処理の追跡が行われます。
もし、マニフェストが交付されなかったり、必要事項が記入されていなかったりした場合、違反行為とみなされ、排出事業者や処理業者に対して罰則が科されます。虚偽の記載が発覚した場合も同様であり、企業の信頼性が損なわれる重大なリスクとなります。
産業廃棄物の違反事例を紹介

廃棄物処理法に違反する行為は、産業廃棄物の処理においても多く見られます。違反事例には、不法焼却、委託基準違反、虚偽のマニフェスト記載などが含まれ、これらの行為が発覚した場合、厳しい罰則が科されることになります。実際の産業廃棄物に関する違反事例について紹介し、その対策について解説します。
◇不法焼却
産業廃棄物の不法焼却は、廃棄物処理法で禁止されている重大な違反行為です。不法焼却は、環境に与える影響が大きく、発覚すれば即座に事業停止命令や罰金が科されるだけでなく、社会的な信用を失うことにもつながります。
ある事例では、工場の廃棄物を適切に処理せずに焼却した結果、近隣住民に健康被害をもたらしたケースがあり、企業は多額の賠償金を支払う事態となりました。
◇委託基準違反

産業廃棄物の処理を外部に委託する際には、適切な基準に従って行わなければなりません。しかし、逆有償取引によって不適切な処理が行われるケースがあります。逆有償取引とは、排出者が処理業者に処理費用を支払うのではなく、逆に処理業者から金銭を受け取ることを指します。
これにより、業者は適切な処理を行わず、不法投棄や不法処理を行う可能性が高まります。こうした委託基準違反が発覚した場合、排出者にも責任が及び、罰則が科されます。
◇産業廃棄物業者の違反
産業廃棄物業者による違反も問題視されています。例えば、再委託基準違反やマニフェストの虚偽記載といった行為が行われた場合、処理業者に対して措置命令が下されることがあります。
再委託基準違反は、許可を受けていない業者に処理を再委託することを指し、これが発覚した場合、業者には罰則が科されます。また、マニフェストの虚偽記載は、処理の実態を隠蔽し、適正な処理が行われていないことを示す重大な違反行為です。このような違反は、環境汚染を引き起こすだけでなく、社会的な信頼を大きく損なう原因となります。
【あわせて読みたい】
▼PCB産業廃棄物の処理期限はいつまで?期限を過ぎても処分できる?
産業廃棄物の罰則に関する注意点と対策

産業廃棄物の処理に関しては、違反行為が発覚すると厳しい罰則が科されるため、企業は特に注意を払う必要があります。意図しない不法投棄やマニフェストの紛失など、意図せずして違反となるケースも多く見られます。罰則に関する注意点とその対策について解説します。
◇意図しない不法投棄

企業が廃棄物を一時的に保管している間に、その保管が長期化し、結果的に不法投棄とみなされるケースがあります。また、委託した業者が不適切な処理を行い、不法投棄してしまう場合もあります。
こうしたリスクを回避するためには、保管基準を遵守することや、信頼性の高い業者に処理を委託することが重要です。業者の選定に際しては、許可の有無や過去の処理実績を確認し、適切な業者に依頼することが求められます。
◇マニフェストの保管義務と紛失した場合
産業廃棄物の処理においては、マニフェストの保管が義務付けられています。マニフェストは、廃棄物の処理過程を追跡するための重要な書類であり、5年間の保管が必要です。
もしこれらの書類のいずれかを紛失すると、保管義務違反に問われ、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。万が一、マニフェストを紛失してしまった場合、再交付は原則としてできません。
しかし紛失した場合、委託した運搬業者や処理業者が保管しているマニフェストのコピーで代用が可能です。紛失が発覚したら、すぐに業者に連絡し、コピーを取得して対応しましょう。
電子マニフェストを導入することで、紛失のリスクを軽減することができ、処理の透明性も向上します。
産業廃棄物管理の要点

産業廃棄物の適正処理は、廃棄物処理法により厳しく規定されており、違反行為が発覚した場合には企業や排出事業者に対して重い罰則が科されます。
意図的な不法投棄だけでなく、保管や書類管理の不備など、思わぬ違反で処罰を受ける事例も少なくありません。ここでは、違反が発生しやすいポイントとその対策について解説します。
◇意図しない不法投棄のリスク

産業廃棄物の一時保管は、適正な基準に従って行わなければなりませんが、保管期間が長期化した場合や、管理が不十分だった場合、結果的に「不法投棄」とみなされることがあります。また、委託した業者が無許可であったり、適切な処理を行わずに不法投棄をしてしまうケースも現実に発生しています。
こうしたリスクを回避するためには、まず自社の保管基準を徹底し、保管場所や期間、管理方法を明確にしておくことが重要です。また、処理委託先を選定する際は、必ず都道府県知事等の許可を持つ業者であることを確認し、過去の実績や行政処分歴なども調査することが求められます。
◇マニフェストの保管義務と紛失時の対応

産業廃棄物の処理には「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の交付・管理が義務付けられており、排出事業者はA票、B2票、D票、E票などの伝票を5年間保存しなければなりません。このマニフェストは廃棄物の流れを追跡し、不適切な処理や不法投棄を防ぐための重要な書類です。
万が一、マニフェストを紛失した場合、保管義務違反とみなされ、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい罰則が科される可能性があります。2018年以前は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金でしたが、現在は法改正により罰則が強化されています。
マニフェストの再発行は原則として認められていませんが、委託先の運搬業者や処分業者が保管している伝票のコピーで代用することができます。紛失が判明したら、速やかに業者に連絡し、必要なコピーを取得しておきましょう。コピーには紛失の経緯をメモしておくと、後のトラブル防止にも役立ちます。
◇電子マニフェストの活用とDX化

紙マニフェストは紛失や管理ミスのリスクが高く、保管場所の確保や管理業務の煩雑さも課題です。こうした課題を解決するため、電子マニフェストの導入が推奨されています。
電子マニフェストならデータでの保存となるため、紛失リスクがなく、業者間のやり取りもスムーズに進みます。第三者機関がデータを保管するため、企業の管理負担も大幅に軽減されます。
また、電子化によって処理状況の追跡や確認が容易になり、コンプライアンス強化や業務効率化にもつながります。今後は産業廃棄物処理業界全体でDX化が進む見通しであり、企業も積極的に電子マニフェストへの移行を進めることが重要です。
◇罰則の厳格化と企業の責任
廃棄物処理法の改正や関連法令の整備により、産業廃棄物処理に関する罰則は年々厳しくなっています。違反が発覚した場合、罰金や懲役だけでなく、行政処分や企業名の公表、社会的信用の失墜といった重大なリスクも伴います。
特に多量排出事業者や大企業の場合、違反内容が公表されることでブランドイメージが大きく毀損される恐れがあります。
こうしたリスクを回避するためには、法令遵守の徹底とともに、社内教育や管理体制の強化、DX化による業務効率化など、総合的な対策が不可欠です。廃棄物管理の専門部署を設けたり、定期的な監査や内部チェックを行うことも有効な手段です。
産業廃棄物処理における違反行為は、意図しないミスでも重い罰則の対象となります。保管基準の遵守、信頼できる業者選定、マニフェスト管理の徹底、電子化による業務効率化など、企業は多角的なリスク対策を講じることが求められます。
今後も法令や社会的要請の変化に柔軟に対応し、持続可能な廃棄物管理体制を構築することが重要です。
【あわせて読みたい】
▼PCB産業廃棄物の処理はどう進める?手続きと起こりえるトラブルを解説
PCB廃棄物処理を検討するならおすすめ業者3選
丸両自動車運送、クリーンシステム、日本海環境サービスの各社は、PCB廃棄物の調査・収集運搬・処理支援を通じて、法令遵守と環境保全に注力し、循環型社会の実現に貢献しています。
◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送株式会社は、全国規模で産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬・処理を行う総合コンサルタント企業です。全国の処分場ネットワークと多彩な車両を活用し、PCBを含む多様な廃棄物の適正処理をワンストップで支援しています。
同社は、PCB廃棄物処理に関して法令に基づく管理体制を確立し、専門講習修了者が対応します。分析や届出書類作成代行、最適な処分方法の提案など、排出事業者の不安を解消するためのサービスを提供しています。
| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |
| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |
| 電話番号 | 054-366-1312 |
| 公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |
また、全国各地で累計約30万本の安定器仕分けを手がけてきました。静岡県の事例では、高濃度と低濃度のPCBを区分することにより、処分にかかる費用の削減につながっています。
全国で収集運搬許可を取得しているため、災害時の迅速な対応が可能です。難易度の高い案件や他社で断られた廃棄物にも柔軟に対応し、循環型社会の実現に向けた貢献を続けています。
丸両自動車運送株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇株式会社クリーンシステム

株式会社クリーンシステムは、PCB廃棄物の調査・処理支援を通じて、環境保全と持続可能な社会の実現に寄与する企業です。PCB含有調査や濃度分析、行政手続きの支援から適正処理まで、一貫したサービスを提供しています。
同社は、PCB廃棄物が特別管理産業廃棄物に区分される特性を踏まえ、全数調査を行い処分コスト削減に貢献しています。さらに、日本PCB全量廃棄促進協会の発起人企業として、業界全体の課題解決にも積極的に取り組んでいます。
| 会社名 | 株式会社クリーンシステム |
| 所在地 | 〒990-0845 山形県山形市飯塚町字中河原1629-5 |
| 電話番号 | 023-644-2228 |
| 公式ホームページ | https://www.csyam.com/ |
環境経営、脱炭素、サーキュラーエコノミーにも注力し、法令遵守と高い技術力で信頼を構築。顧客ごとに最適な処理計画を提案し、持続可能な社会の実現を目指しています。
こちらも併せてご覧ください。
◇日本海環境サービス株式会社
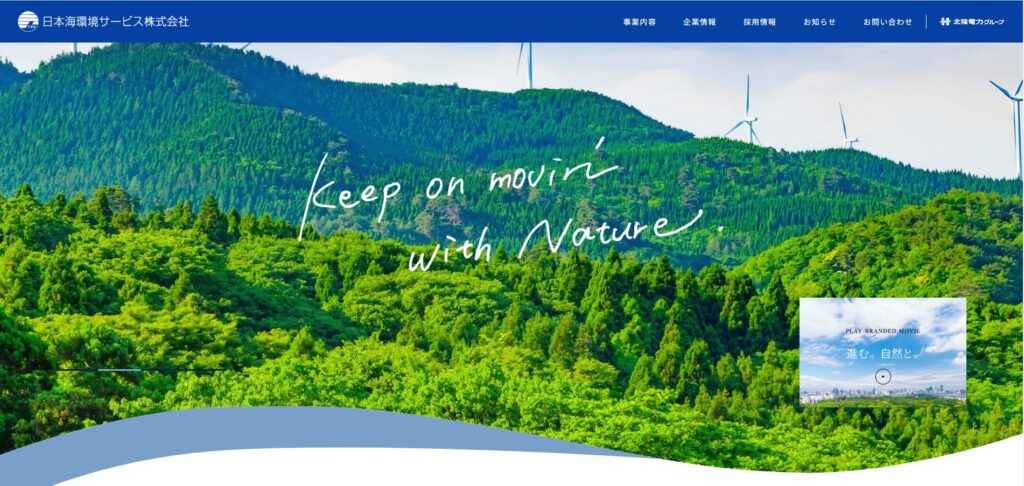
日本海環境サービス株式会社は、北陸電力グループの一員として富山県を拠点に環境保全事業を展開する企業です。1992年の設立以来、水域・自然環境調査や土壌汚染調査、環境機器販売、造園工事など、多岐にわたるサービスを提供しています。
同社は低濃度PCB汚染物処理に強みを持ち、課電自然循環洗浄技術を活用して変圧器やコンデンサの無害化を支援。絶縁油の抜油・分析から新油注入、行政手続きまでをワンストップで対応します。PCB含有塗膜や廃棄物の分析・処分も一括で行い、複数県で特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しています。
| 会社名 | 日本海環境サービス株式会社 |
| 所在地 | 〒930-0848 富山県富山市久方町2-54 |
| 電話番号 | 076-444-6800 |
| 公式ホームページ | https://www.nes-env.co.jp/ |
地域社会の信頼を得る環境ソリューション企業として、安全と環境対策を重視。顧客に寄り添った課題解決と確かな技術力で、持続可能な社会の実現に貢献しています。
こちらも併せてご覧ください。
まとめ

廃棄物処理法は、産業廃棄物や一般廃棄物を適切に処理し、環境保全を図るために制定された重要な法律です。排出事業者や処理業者には厳しい基準が設けられ、廃棄物の収集、運搬、処理を適切に行う責任が課されています。
しかしながら、許可のない業者への委託や無許可営業、不法投棄・焼却などの違反行為は未だ多く、厳しい罰則が科されるケースが続いています。特に、不法投棄や不法焼却は環境に深刻な影響を与えるため、厳しい監視と取り締まりが行われており、発覚すれば罰金や事業停止命令が科される可能性があります。
また、マニフェストの適正な管理や保管も重要であり、違反があった場合には罰則の対象となります。企業はこれらのリスクを避けるため、許可を受けた信頼性の高い業者に委託し、保管基準やマニフェストの適正な管理を徹底する必要があります。
この記事を読んでいる人におすすめ