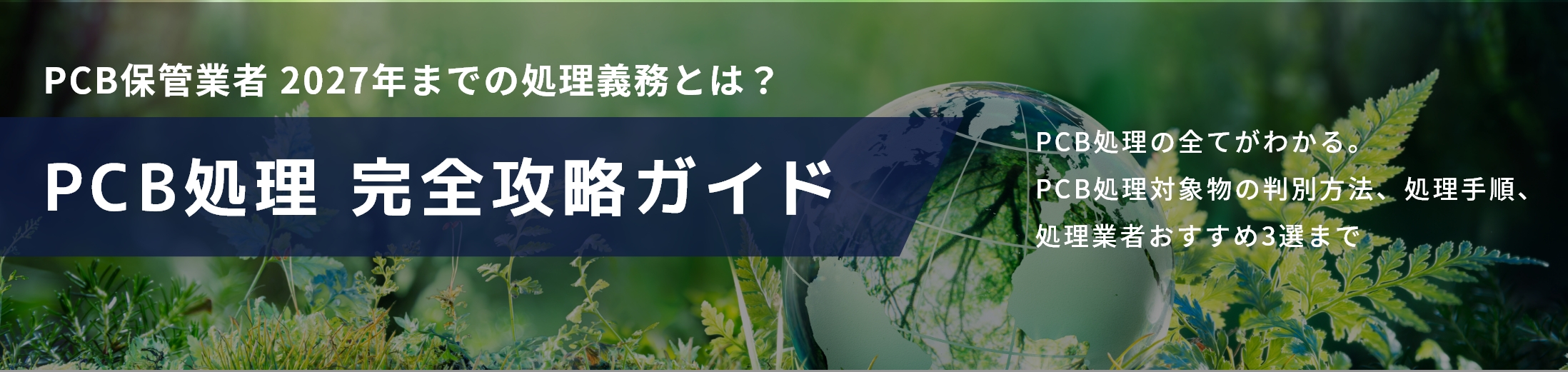ストックホルム条約(POPs条約)は、環境と健康保護を目的に、有害化学物質の使用や排出を国際的に規制します。PCB廃棄物の適切な処理が求められ、リユースやリサイクルは禁止されています。日本ではPCB処理が遅れており、今後5年間で無害化を目指しています。
目次
ストックホルム条約におけるPCB処理
ストックホルム条約(POPs条約)は、環境と人類の健康を保護するために、有害な化学物質の使用や排出を規制する国際的な取り組みです。その中でも、PCB(ポリ塩化ビフェニル)の適切な処理は特に重要な課題となっています。
◇ストックホルム条約(POPs条約)の背景と方向性
ストックホルム条約(POPs条約)は、2001年に採択された国際的な条約で、残留性有機汚染物質(POPs)の毒性や環境への長期的影響を削減することを目的としています。この条約は、環境中で分解されにくく、長期間残留し、生態系や人間の健康に悪影響を及ぼす化学物質を国際的に規制します。
条約では、有害物質の製造、使用、輸出入、廃棄などを包括的に管理することを目指しており、各国にはこれらの物質に関する監視や報告の義務があります。国際社会全体で協力し、環境への排出量を削減する取り組みを推進しています。
◇POPsとは
POPs(残留性有機汚染物質)とは、環境中で分解されにくく、長期間残留する有害な化学物質です。これらの物質は生物に対して強い毒性を持ち、国際的に深刻な環境問題とされています。
代表的なPOPsには、ダイオキシン類、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、かつて広く使用されていたDDTやアルドリンなどがあります。これらの物質は環境中に長く残り、人間の健康や生態系に深刻な影響を及ぼすため、国際的な規制が必要とされています。
日本と海外で異なるPCB廃棄物処理基準

POPs条約は、POPsの管理と廃棄に国際基準を設定しています。PCB含む廃棄物は適切に処理し、リユースやリサイクルは禁止です。PCBの処理基準は国によって異なり、日本は0.5ppm、オランダは1ppmなど、規定値が異なります。
◇POPs条約の規定
POPs条約は、残留性有機汚染物質(POPs)の管理と廃棄について国際的な基準を設定しています。具体的には、以下のポイントが重要です。
まず、PCBを含むPOPs廃棄物は、環境や健康に悪影響を及ぼさないよう、適切に収集、運搬、保管しなければなりません。また、POPsの有害性を除去するために、適切な分解処理を行う必要があります。分解が難しい場合や含有量が少ない場合には、環境に配慮した他の処分方法が求められます。
POPsを含む廃棄物のリユースやリサイクルは禁止されています。特にPCBは有害な化学物質であるため、厳格な管理のもとで廃棄する必要があります。
処分期限については、PCB廃棄物の最終処分期限が2028年と定められています。また、POPs条約第4回締約国会議で規定対象物質として指定された「ブロモジフェニルエーテル群」については、一定の条件を満たし、環境に悪影響を及ぼさない方法でのリサイクルや使用が認められています。
◇各国で異なるPCBの処理基準
PCBの処理基準は、油中のPCB濃度を特定のレベル以下に保つことを指します。これは、PCBが環境や健康に及ぼす影響を最小限に抑えるために設定された基準です。PCB濃度の規定値は国によって異なります。
例えば、日本では0.5ppm、オランダでは1ppm、アメリカやカナダでは2ppm、イギリスやドイツでは10ppm、フランスやオーストラリアでは50ppmとされています。
各国のPCB使用量と海外の処分状況
PCBの使用量は、スイスが最も多く約230 kg/km²で、日本が次いで約100 kg/km²です。海外では、EU、アメリカ、カナダなどが処分を進めており、日本は1999年末から処理が遅れており、現在も1ヵ所の高温焼却施設と4ヵ所の化学処理施設を稼働しています。
◇各国のPCB使用量
PCBの使用量を国土面積当たりで見ると、スイスが約230 kg/km²で最も多く、次いで日本が約100 kg/km²、EUが約70 kg/km²、アメリカが約250 kg/km²です。しかし、スイスは国土面積が日本の約9分の1なので、実質的には日本が最も多くのPCBを使用しています。
対照的に、ニュージーランド、カナダ、ノルウェー、オーストラリアなどは、PCB使用量が5 kg/km²未満と非常に低い数値にとどまっています。
◇海外の処分状況
EUでは、2009年末までにPCBの処分を完了する予定であり、対象区域外では政府の協力が見込まれています。さらに、船上での焼却は禁止されています。アメリカでは、複数の焼却施設でPCBの焼却処理が行われており、化学処理も認められています。また、移動型処理施設に関する連邦規則も整備されています。
カナダでは、固定型と移動型の焼却炉が稼働中です。イギリスは、1999年末までにPCBの処分を終了する予定です。また、EU諸国以外からのPCBの輸入は禁じられています。
フランスとドイツも、2009年末までにPCBの処分を完了する予定であり、ドイツでは4カ所の指定有害廃棄物焼却場で処理が行われています。
スウェーデンでは、PCBの焼却処理が進行中です。オーストラリアは、高温焼却計画を中止し、3カ所の化学処理施設を設置しました。リスクの高いものから処理を行い、2009年までに処理を完了する予定です。計画策定段階からは、住民の参画も進めています。
日本では、1999年末から一部企業による化学処理を除き、PCB処理が進んでいません。そのため、国は中小事業者のPCB廃棄物について、5年間で50%の無害化を目指しています。
また、大手事業者には自社処理を推進しており、現在は1ヵ所の高温焼却施設と4ヵ所の化学処理施設が稼働しています。
日本のPCB廃棄物処分が厳しい理由とは?
日本ではPCB使用量が多かったため厳しい処理基準が設けられています。処理基準は国際基準を参考に、安全性を高めるために0.5mg/kg以下のPCB濃度と環境影響の回避が求められています。海外でもPCB漏洩事例があり、カナダやベルギーでは大規模な汚染事故が発生し、処分強化が進められています。
◇ 日本のPCB廃棄物処分が厳しい理由
日本ではPCBの使用量が多かったため、厳しい処理基準が設けられています。PCBは1970年代まで広く電気機器や変圧器に使用されていました。日本の処理基準は、国際基準や技術評価を参考にして、安全性を高めたものです。
具体的には、技術的に実現可能で、処理後の油のPCB濃度が0.5mg/kg以下、環境に影響を与えないレベルであること、そして適切な分析方法で基準達成を確認することが求められています。
◇海外の漏洩や混入の事例
日本では「カネミ油脂事件」というPCB汚染事件がありましたが、海外でもPCB漏洩や混入の事例が発生しています。
1985年には、カナダのオンタリオ州でPCB入りトランスから汚染油が漏れ、土壌や地下水が汚染されました。この事故は1000億円以上の被害をもたらし、水道の閉鎖や市民生活への影響もありました。PCBは長期間残留し、汚染地下水の長期的な影響が懸念されています。
1999年には、ベルギーの工場で食用油のリサイクル中にPCB入りトランス油が混入し、食肉への汚染の可能性が高まりました。そのため、影響を受けた商品をすべて回収・処分する必要が生じました。
この問題を受けて、ベルギーではPCBのモニタリングや混入の恐れのある家畜飼料の使用禁止、PCB廃棄物の処分強化が進められています。
ストックホルム条約(POPs条約)は、環境と人類の健康保護を目的とし、有害な化学物質の使用や排出を国際的に規制する取り組みです。2001年に採択され、残留性有機汚染物質(POPs)の毒性や長期的な影響を削減することが目指されています。
POPsは環境中で分解されにくく、長期間残留するため、国際的な規制が必要です。代表的なPOPsには、ダイオキシン類やPCB(ポリ塩化ビフェニル)があります。
POPs条約では、PCBを含む廃棄物の適切な収集、運搬、保管が求められ、リユースやリサイクルは禁止されています。特にPCBは有害であるため、厳格な管理のもとで廃棄されるべきです。
最終処分の期限は2028年に設定されており、特定の条件を満たす場合にはリサイクルが認められることもあります。
PCBの処理基準は国によって異なり、日本では0.5ppm、オランダでは1ppm、アメリカやカナダでは2ppm、イギリスやドイツでは10ppm、フランスやオーストラリアでは50ppmとされています。
各国でのPCB使用量や処分状況にも差があります。スイスは国土面積当たりのPCB使用量が最も多く、日本が次いで多いです。一方、ニュージーランドやカナダなどは非常に低い使用量です。
海外の処分状況では、EUは2009年末までにPCBの処分を完了する予定で、船上での焼却は禁止されています。アメリカでは複数の焼却施設で処理が行われ、カナダでは固定型と移動型の焼却炉が稼働中です。
イギリスやフランス、ドイツも2009年末までに処分を完了する予定で、ドイツでは4カ所の指定有害廃棄物焼却場が設置されています。オーストラリアは高温焼却計画を中止し、化学処理施設を設置しました。
日本では、1999年末から一部企業による化学処理を除き、PCB処理が進んでおらず、現在も1ヵ所の高温焼却施設と4ヵ所の化学処理施設が稼働しています。国は中小事業者のPCB廃棄物について、5年間で50%の無害化を目指しており、大手事業者には自社処理を推進しています。