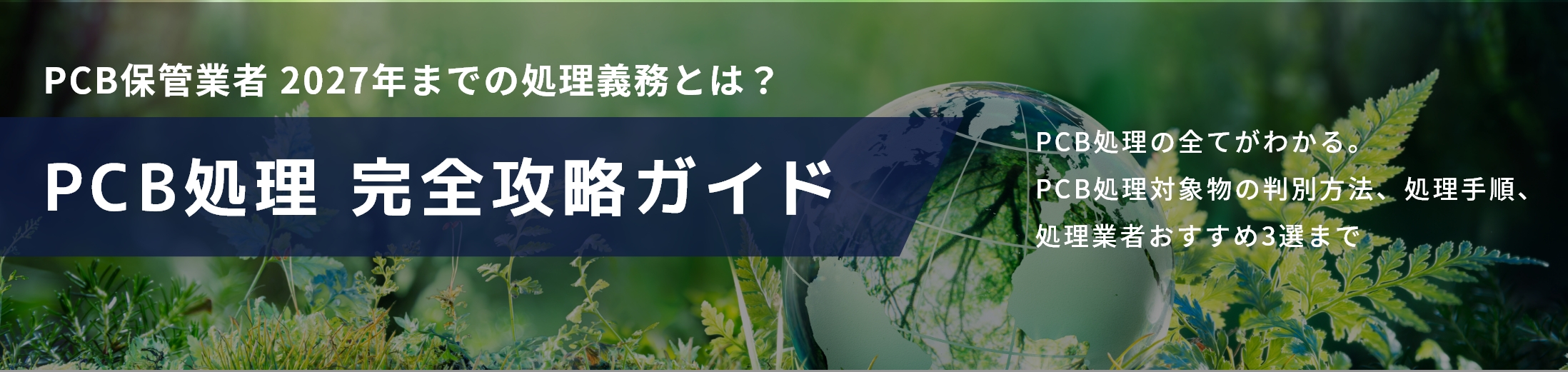PCBはかつて広く使用されていましたが、その後環境汚染と健康被害の問題が浮上し、1972年に製造が禁止されました。その後、処理施設の整備や法整備が行われ、全国的なPCB廃棄物処理体制が整備されました。しかし、処理の遅れや課題も浮かび上がり、改正が行われるなど、政府の取り組みが進められています。
目次
かつては広く使用されていたPCB
かつては広く使用されていたPCBは、その優れた絶縁性や耐熱性、非水溶性などの特性から、機械部品の潤滑油や冷却剤として幅広く利用されていました。
◇PCBの性質と過去の用途
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、ビフェニルの水素が塩素に置換した化合物の総称です。外見は無色透明で、油のような性質を持ちます。これに加えて、酸やアルカリに変化せず、高い耐熱性、絶縁性、非水溶性を持っています。昔はこれらの特性から、工業用オイルとして広く利用されており、機械部品の潤滑油や冷却剤として長期間使用されていました。
さらに、PCBは不燃性を持っており、火災の原因になりにくい性質も備えています。そのため、さまざまな産業分野で絶縁材や化学樹脂の製造にも利用されていました。昭和29年に日本でPCBの生産が始まり、ピーク時には年間約11,000トンも生産されていました。
◇PCB汚染の発覚
1966年以降、世界各地で魚類や鳥類の体内からPCBが検出され、地球全体がPCBによって汚染されていることが明らかになりました。特に1968年のカネミ油症事件では、食用油に誤って混入したPCBが大規模な健康被害を引き起こしました。
PCBは生物の体内に蓄積しやすく、食物連鎖を通じて人体に取り込まれると中毒症状が現れます。その後、日本では1972年にPCBの製造が禁止され、国際的な取り組みとして2001年にはPCBを含む残留性有機汚染物質の廃絶・削減を目指す「POPs条約」が採択されました。
これらの事件や条約の成立を通じて、PCBの毒性と地球規模の環境汚染が広く認識されるようになりました。
PCB製造禁止と処理開始

画像出典先:環境省_ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
PCBの有害性が認識され、1972年に日本ではPCBの製造が禁止されました。これに伴い、PCB廃棄物の処理が喫緊の課題となり、政府は処理を開始するための措置を講じました。
◇PCB製品の回収と製造禁止
日本では1972年(昭和47年)にPCBの製造が中止され、1974年(昭和40年)には製造や輸入が禁止されました。そして、世界でもPCBによる環境汚染が懸念され、2001年に締結されたストックホルム条約では、2028年までにPCBを全廃することが決定します。これにより2001年には国内でもPCB特措法が制定され、国が中心となってPCBを産業廃棄物として処理する体制の整備が行われることになりました。
◇停滞したPCB廃棄物の処理
大量のPCBを含む電気機器が廃棄物となりましたが、民間の処理施設が不足していたため、30年以上にわたり事業者が保管を余儀なくされます。こうしたことから、通商産業省の指導のもと、(材)電機ピーシービー処理協会が設立され、PCBの回収・処理体制の構築が試みられます。
しかし、処理施設の建設が進まず、地方公共団体や住民の理解が得られなかったため、PCB廃棄物の保管が続いていました。保管中の高圧トランス・コンデンサの台数は不明・紛失が多く、特に大量の台数が行方不明になっています。そのため、保管中や使用中のPCB機器の所在確認をして、未届出の事業者の把握や情報共有が必要でした。
処理施設の誕生と法律の制定
PCB廃棄物の処理に向けた取り組みが本格化し、処理施設の設立が始まりました。同時に、適切な処理を促進するため、政府は法律の制定に取り組み、PCBに関する規制を整備していきました。
◇北九州をきっかけに全国に処理背施設が建設
2000年(平成12年)12月、国は北九州市に対して、西日本17県のPCB廃棄物を処理する施設の建設を求めました。北九州市は市民や議会からの意見を広く聴取し、安全性を検討した後、2001年10月に国の安全基準を守る条件付きで施設の建設を受け入れました。
そして、北九州市では安全性を最優先し、市民とのコミュニケーションを大切にして、2004年から10年間、PCBの漏洩や健康被害がなく、順調に処理が進められています。
◇PCB廃棄物処理に関する法律の制定
2001年(平成13年)6月22日に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB措置法)が制定され、同年7月15日から施行されました。PCB措置法により、PCB廃棄物を所有する事業者は、保管状況などを報告する義務が課せられ、一定期間内に適切に処分しなければなりません。
そして、法律の施行に伴い、国は日本環境安全事業株式会社(現在の中間貯蔵・環境安全事業株式会社、通称JESCO)を通じて、拠点となる処理施設を整備することになりました。
その後、豊田、東京、大阪、北海道にも処理施設が建設され、全国的なPCB廃棄物処理体制が整うようになったのです。
PCB廃棄物処理の遅れとPCB特措法の改正
PCB廃棄物の処理体制が整った後も、様々な要因からPCB廃棄物処理の遅れがみられ、政府は迅速な対応を迫られました。ここでPCB特措法の改正に至った経緯について解説します。
◇PCB特措法が制定されるも残る課題
国はPCBについて法整備を進め、処理期限を設けるなどして処理を促しました。しかし、想定を超えるPCB廃棄物が存在し、一部の事業者がESCOに処分を委託していないことや、まだ高濃度PCBを使用した製品を使っている事業者もいることが明らかになりました。
そのため、PCB廃棄物の処理が期限内に完了するためには追加的な措置が必要とされ、PCB措置法が改正されました。この改正によって、残る課題に対処するための新たな取り組みが促進されることになります。
◇PCB措置法の改正
2019年(令和元年)の法改正では、これまでの高濃度PCB廃棄物の定義が見直され、「可燃性の廃棄物で、PCBを含む部分が重量の0.5%を超え10%以内のもの」が低濃度PCB廃棄物に再分類されます。
これにより、低濃度PCB廃棄物の場合、処分方法の規制が緩和され、処分期限も延長されることになりました。ただし、金属くずやガラスくずなどの非可燃物の高濃度PCB廃棄物は、依然として従来通りの区分となりますので、注意が必要です。
また、低濃度PCB廃棄物の処理温度条件も引き下げられましたが、新たに0.5%超~10%以下のPCB廃棄物については、今まで通り、1,100℃以上での処理が求められます。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、その優れた絶縁性や耐熱性、非水溶性から機械部品の潤滑油や冷却剤として利用されていました。しかし、1960年代後半からPCBの環境汚染が明らかになり、特に健康被害を引き起こす事例が多発しました。
1972年に日本でPCBの製造が禁止され、国際的な取り組みも始まりました。その後、PCB廃棄物の処理が課題となり、日本ではPCB措置法が制定されました。しかし、民間の処理施設が不足し、廃棄物の保管が続きました。
2000年代に入り、処理施設が整備され、全国的なPCB廃棄物処理体制が整備されました。しかし、処理の遅れや残存するPCB廃棄物の問題が浮上し、PCB特措法が改正されました。2019年の法改正では、低濃度PCB廃棄物の処理規制が緩和され、処分期限が延長されました。これにより、残る課題に対処する新たな取り組みが促進されることとなりました。